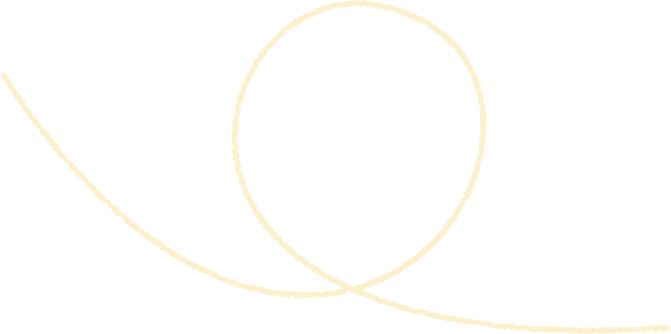
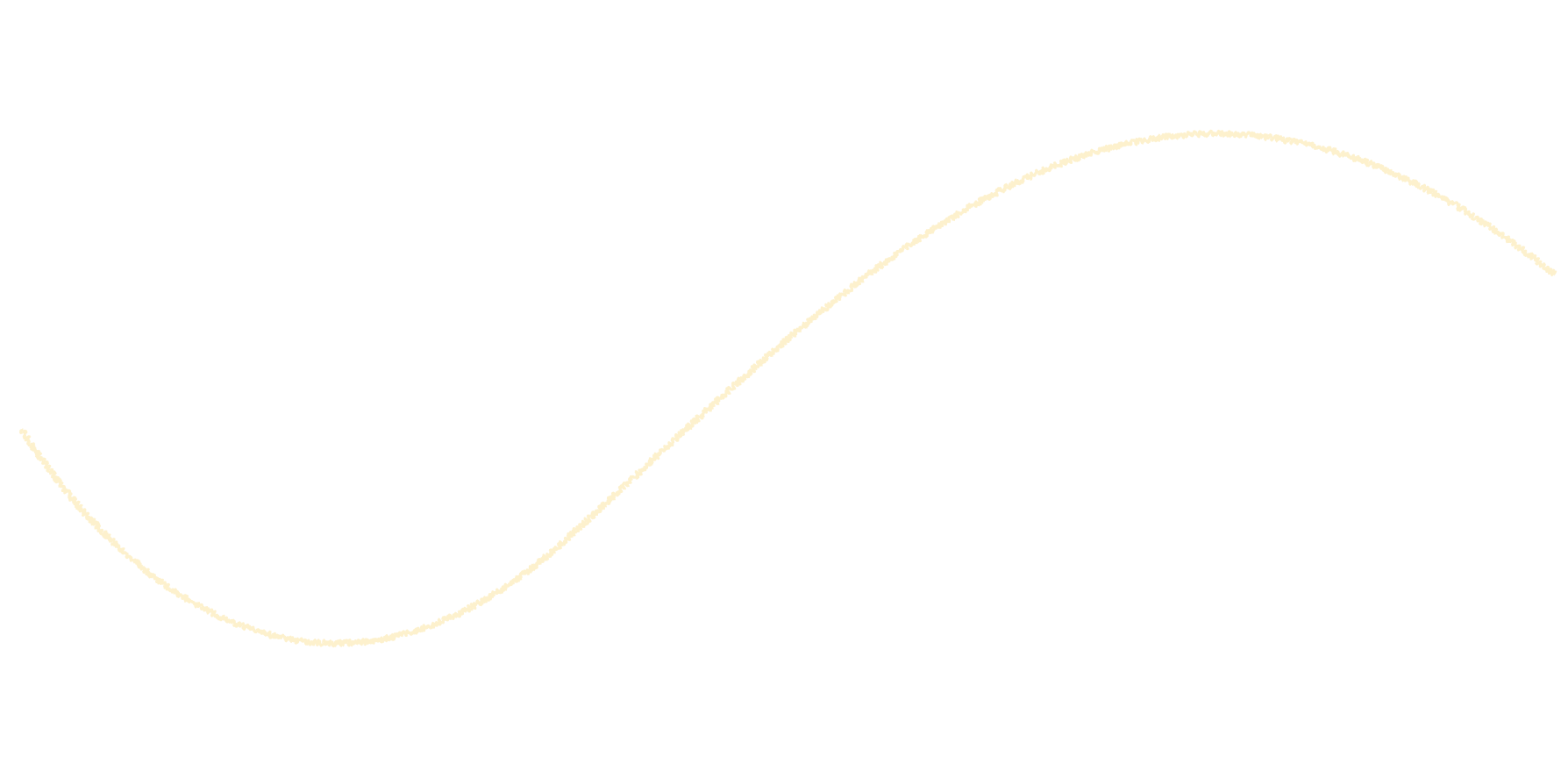
文化服装学院では、現在600名以上の留学生が学んでいます。
出身国は中国・韓国・台湾などのアジア圏から、ヨーロッパやアメリカなど多岐にわたります。ニットデザイン科でも、2年生、3年生と合わせて中国から3名、韓国から7名、インドネシアから1名の学生が日々勉強に励んでいます。
そんなわけで、今回はニットを学ぶ留学生にフォーカス。なぜニットを学んでいるのか、それぞれの国のニット事情なども含めて聞いてみました!
留学生の多くは、まず日本語学校で日本語を学んでから文化服装学院に入学してきます。そして文化では日本人の学生と席を並べ、日本語でファッションの専門教育を受けています。
いつも驚かされるのは日本語の上達の早さや色彩感覚の豊かさ、コミュニケーションスキルの高さ。日本人の学生と冗談を言い合ったり、敬語を上手に操ったり。海外での生活は何かと苦労も多いはずなのに、熱心にニットのものづくりに打ち込んでいます。
日本人学生も、そんなクラスメイトに刺激を受けているのは明らか。すっかりクラスに溶け込んだ留学生と、プライベートでも一緒に遊んでいたりと仲良く過ごしているようです。
それでは留学生の皆さんの作品を紹介します。文化服装学院を選んだきっかけなど、私も今回初めて聞く話もあり、非常に興味深かったです。
キム ウン(2年生、韓国)
—ニットデザイン科を選んだきっかけ
手編みから機械編み、コンピュータニットまで幅広くニットについて学べるので、ニットデザイン科に進級しました。
—初めて編み機を使った感想
最初は編み機のさまざまな機能を完璧には理解できず、苦労しました。10か月ほど経った今では、いろいろな機能を覚えられたおかげできれいに編めるようになり、すごくうれしいです!
 色、風合いの異なる糸で表情豊かに仕上げた、機械編みのスカート。スカートだけならロマンティックですが、手編みの黒いニットと組み合わせるとパンクな雰囲気に
色、風合いの異なる糸で表情豊かに仕上げた、機械編みのスカート。スカートだけならロマンティックですが、手編みの黒いニットと組み合わせるとパンクな雰囲気に クラシックなアーガイル模様を、自分らしく表現することに挑戦したプルオーバー。編み機でインターシャをするのは難しいこともあり、別に編んだモチーフを縫い付けて表現しました。擦り切れやすい肘の部分には、補強と装飾を兼ねたダーニング※をしています
クラシックなアーガイル模様を、自分らしく表現することに挑戦したプルオーバー。編み機でインターシャをするのは難しいこともあり、別に編んだモチーフを縫い付けて表現しました。擦り切れやすい肘の部分には、補強と装飾を兼ねたダーニング※をしています※ダーニングの特別講義
ニットデザイン科では毎年、ニットデザイナー・作家の野口光先生によるダーニングの特別講義を実施しています。学生は各自ダーニングしたいものを持参し、さまざまな装飾ダーニングの技法を学びます。


チョ ウォンビン(3年生、韓国)
Instagram:@cho0nebin
ーニットデザイン科を選んだきっかけ
韓国の大学卒業後に、手作りの帽子屋で働き始め、そこで帽子を編むようになりました。それがニットの世界に入りたいと思ったきっかけです。
ニットの知識や技術を身につけたらどんなに面白い表現ができるか興味を持ち、ニットについて幅広く学ぶことができる文化服装学院に留学しました。
—韓国と日本のニット、ここが違う!と感じること
韓国の百貨店で山形のファクトリーブランドでもあるM.&KYOKO※のビーニー帽を目にし、手作り感たっぷりで、なおかつ繊細なデザインで驚いたことがあります。今は学校でニットを学んだおかげで、その帽子がコンピュータニットのどんな編み方で作られているのかを想像できるようになりましたが、その頃は気になって仕方なかったです。
日本は韓国に比べて、繊細な編み地やディテールのニットウェアが多いと思います。
あと、学校の授業も違っていて。韓国では棒針編みはアメリカ式ですが、日本はフランス式なんですよ!
※M.&KYOKOは、文化服装学院の卒業生でもある佐藤正樹さんが代表を務める紡績・ニットメーカー佐藤繊維(株)のオリジナルブランドです。
 テーマは「石・風・葉・雲」。石の凹凸感を表現するために細編みや長編みをランダムに編み続けた、かぎ針編みのカーディガンです。ポイントは大好きな写真集『FLORA』(ニック・ナイト撮影)を参考に、風に当たってぐるぐる回る風車のような植物の葉を表現したことです。編み上がった作品を見た瞬間、ところどころに点在する白い編み地部分は雲のようにも見えました
テーマは「石・風・葉・雲」。石の凹凸感を表現するために細編みや長編みをランダムに編み続けた、かぎ針編みのカーディガンです。ポイントは大好きな写真集『FLORA』(ニック・ナイト撮影)を参考に、風に当たってぐるぐる回る風車のような植物の葉を表現したことです。編み上がった作品を見た瞬間、ところどころに点在する白い編み地部分は雲のようにも見えました
次は中国からの留学生です。広大な中国のあらゆる地域から日本に来ています。
トウ カジョウ(3年生、中国)
Instagram:@chache12138
—中国での暮らしと、ファッションに興味を持ったきっかけは?
中国・上海の出身。家族はバッグ工場を経営しています。高校2年生の頃にsacai、三宅一生のような日本のファッションにハマり、高校卒業後に文化服装学院に入学しました。
2年次の進級の際には、布帛(アパレルデザイン科やアパレル技術科)とニットのどちらを専門的に学ぶかで悩みましたが、最終的にニットデザイン科に進級しました。
—ニットで好きな技法は?
ニットで一番好きなのは定番の棒編み。棒編みはニットの基礎です。いろいろな技法がありますし、一段一段ごとに努力を重ねていく過程はすごく大事。テレビを見ながら編み物をする穏やかな時間は、自分の宝物です。
—中国のニット事情
中国はアパレルの生産大国です。まわりにも手編みができる人がたくさんいますよ。イタリア糸のような高級糸だけでなく、化繊や普通の羊毛も安く手に入れることができます。
ただ、アパレル生産大国とはいえ、ファッションの独創性はまだまだ足りないと思うこともあります。
 このカットソーカーディガン(コンピュータニット)は、アメリカのグラフィティカルチャーに影響を受け、ダブルジャガードで編み上げました。ドット絵のテクニックと黒と白だけを使い、ストリートカルチャーのクールさを再現したつもりです
このカットソーカーディガン(コンピュータニット)は、アメリカのグラフィティカルチャーに影響を受け、ダブルジャガードで編み上げました。ドット絵のテクニックと黒と白だけを使い、ストリートカルチャーのクールさを再現したつもりです 宮廷の花壇をイメージした丸ヨークセーター(棒針編み)です。建築と自然の両方からインスピレーションを得て、ニットの凹凸感が生む柄と丸ヨーク独特のリピート配色でバランスよく編みました
宮廷の花壇をイメージした丸ヨークセーター(棒針編み)です。建築と自然の両方からインスピレーションを得て、ニットの凹凸感が生む柄と丸ヨーク独特のリピート配色でバランスよく編みましたタン チェン(3年生、中国)
Instagram:@boman3556
—日本の文化服装学院に入学するまでの経緯
中国の大学では、デザインとは全く関係のないことを学んでいましたが、卒業後に日本語を学び、他の専門学校でファッションを学びました。
次第にニットに興味を持つようになり、ハンドニットからコンピュータニットまで幅広く学べる文化服装学院に入り直しました。
ーニットを選んだきっかけ
最初の服飾専門学校でファッションデザインを学んでいた頃、アーティスト・さぶ さんの個展「yarn yarn」を見に行きました。
ニットを使った色とりどりのアートピースを見た瞬間に、幼い頃に叔母や祖母から手編みのセーターやニット小物をもらった記憶が蘇り、心の琴線に触れたことをきっかけに、ニットについて体系的に学びたいと思うようになったんです。
 春、植物が芽吹くことをイメージして制作した、2年次修了作品です。セーターとショートパンツを主にかぎ針で編んでいます。つぼみを表現するため、ショート丈のセーターは玉編みと引き返し編みを駆使して、丸みのあるフォルムに仕上げました
春、植物が芽吹くことをイメージして制作した、2年次修了作品です。セーターとショートパンツを主にかぎ針で編んでいます。つぼみを表現するため、ショート丈のセーターは玉編みと引き返し編みを駆使して、丸みのあるフォルムに仕上げました
—好きな技法は?
好きな技法は、かぎ針編みと家庭用編み機です。
かぎ針はどこにいても編めます。小さな棒を頼りに色の違う毛糸を組み合わせ、頭の中に記憶させるだけで同じ模様が完成するのはとてもすごいことだと思うのです。基本的なJIS記号でできる表現がたくさんあり、大きな可能性が広がっていることが、かぎ針編みが好きな大きな理由です。
家庭用編み機は今まで見たことのなかった機械で、最初はとても難しかったのですが、繰り返し練習するうちに面白さがわかるようになりました。棒針よりも早く仕上がり、表現も豊かになるのが楽しいです。

—中国の手編み状況
中国でも、日本と同じようにニットを編める人は少ないです。
母は長いこと編み物をしていませんでしたが、私が中国を離れてからは再び編み物を趣味にするようになりました。もともとは手編みの専門店に通い、そこで何人かのおばちゃんたちに編み物を習っていたそうです。母の話を聞くと、学校で学ぶような表記の仕方や目数の計算など、厳密なプロセスはないそうです。店長からも編み方を教わっていましたが、編み物を習う人が少なくなり、昨年店を閉めたそう。とても残念です。
 かぎ針編みカーディガン
かぎ針編みカーディガン
最後はインドネシアからの留学生を紹介します。
ラマワティ ミッシェル アウリア(3年生、インドネシア)
Instagram @hanais.m
—日本に来たきっかけ
日本のロリータファッションが好きなこと。さらに服の勉強もしたくて文化服装学院を選びました。
—ニットデザイン科を選んだ理由
1年次に服の作り方を勉強していく中で、ニットデザイン科のファッションショーや作品を見学し、ニットでいろいろなものを作れることを知り、もっとニットについて知りたいと思い選びました。
ただ、インドネシアでは日本のように冬もののセーターなどは着ないので、帰国後にどんな仕事ができるのかについては心配でした。でも、インドネシアではニットに詳しい人は多くはないし、ニットはセーターなどの冬物だけではなく、下着、靴下、アクセサリーも作れると思ったことが決め手です。
 編み方自由で制作したかぎ針編みのカーディガンです。パターンを作成し、それに編み地を合わせながら編みました。いろいろな素材を使いましたが、本当に楽しく編めました!みなさんも残った糸があれば、たまには思いのままに編むことをおすすめします
編み方自由で制作したかぎ針編みのカーディガンです。パターンを作成し、それに編み地を合わせながら編みました。いろいろな素材を使いましたが、本当に楽しく編めました!みなさんも残った糸があれば、たまには思いのままに編むことをおすすめします
—ニットで好きな技法と理由
かぎ針編みが好きですね。最初は苦手でしたが、練習を重ねたらかぎ針の方が自由に編めると感じます。計算なしで自由に編めるのも好きな理由です。
棒針編みには棒針編みの楽しさがありますし、アフガン編みにもまた違う楽しさがあります。いろいろな技法を習得できることは本当に楽しいです。
 プライベートで習っているフラワーアレンジメントとニットを組み合わせたヘッドピース
プライベートで習っているフラワーアレンジメントとニットを組み合わせたヘッドピース
ーインドネシアと日本のニットの違い
インドネシアは一年中暑い国。ニットは服ではなく、バッグや帽子の方が多いです。それに毛糸ではなく、藤や竹を使っても編むことが多いので、日本のニットとはイメージが違いますね。編み方は同じだけど素材だけ違うって感じかな。それもニットの面白いところで、素材が違うと全く違うものを作り出せます。
 プライベートで習っているフラワーアレンジメントとニットを組み合わせたブーケ
プライベートで習っているフラワーアレンジメントとニットを組み合わせたブーケ
おわりに
留学生特集はいかがでしたか?
国によってニットを取り巻く環境は多少異なりますが、「編む楽しさ」は世界のどこにおいても同じなのでしょう。さながら共通言語のようだと思いませんか?
また今回の記事をまとめるにあたり、留学生はたくさんの文章を寄せてくれました。日本語で書くのは、本当に大変だったと思います。みんなの文章からはさまざまな思いが溢れてきて、本当は全文を載せたいくらいなのですが、あまり長くなりすぎるのも、と。
卒業後は日本で就職したり、母国に戻ってファッションに携わったりと進路はさまざまですが、今の在校生の中にはコロナ禍でなかなか入国出来ず、当初はオンラインで授業を受けていた学生もいます。限られた文化服装学院での学生生活を満喫してほしい!と思うばかりです。
次回は卒業のシーズンにまつわる、さまざまな取り組みを紹介したいと思います。
文化服装学院 ニットデザイン科専任教授。文化服装学院ファッション工科専門課程ニットデザイン科。編物科・ニッティング科・産業ニットデザイン科と時代とともに名称を変え、ニット業界を支える人材を長年輩出しています。そのニットデザイン科学生達の奮闘を講師目線でお届けします。
https://www.bunka-fc.ac.jp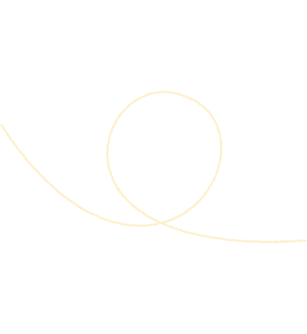
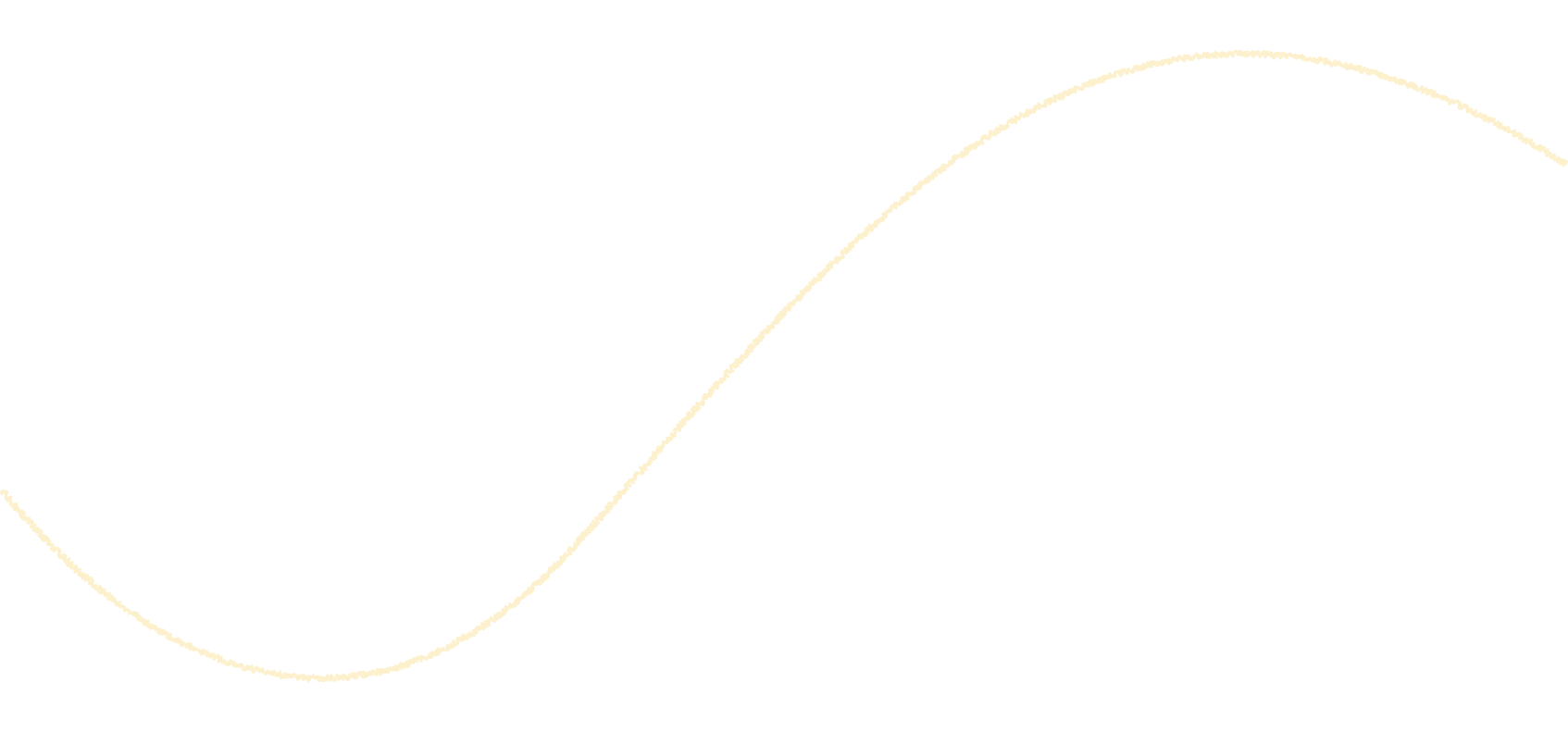
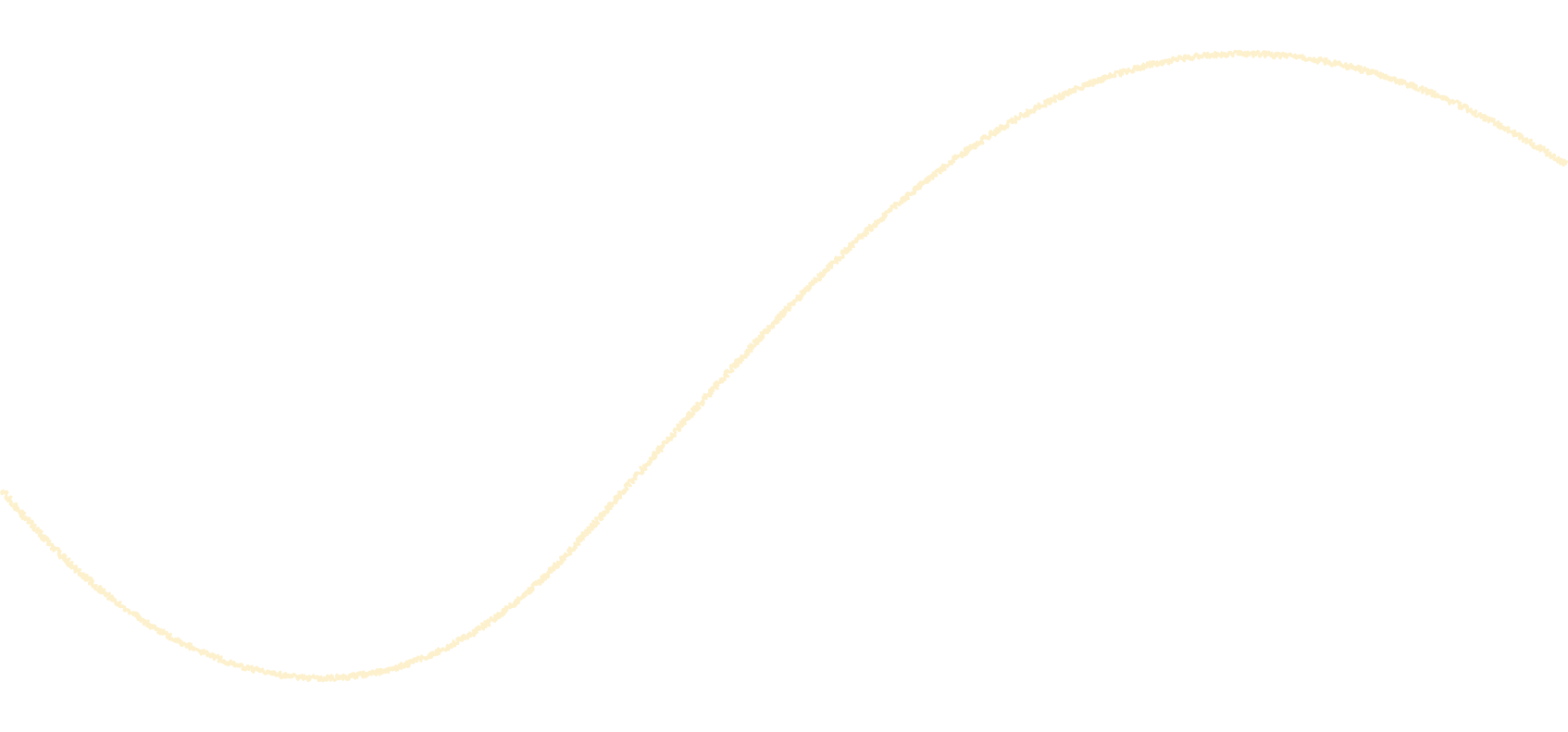
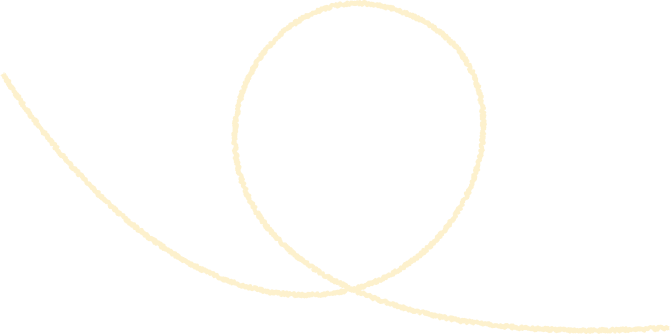
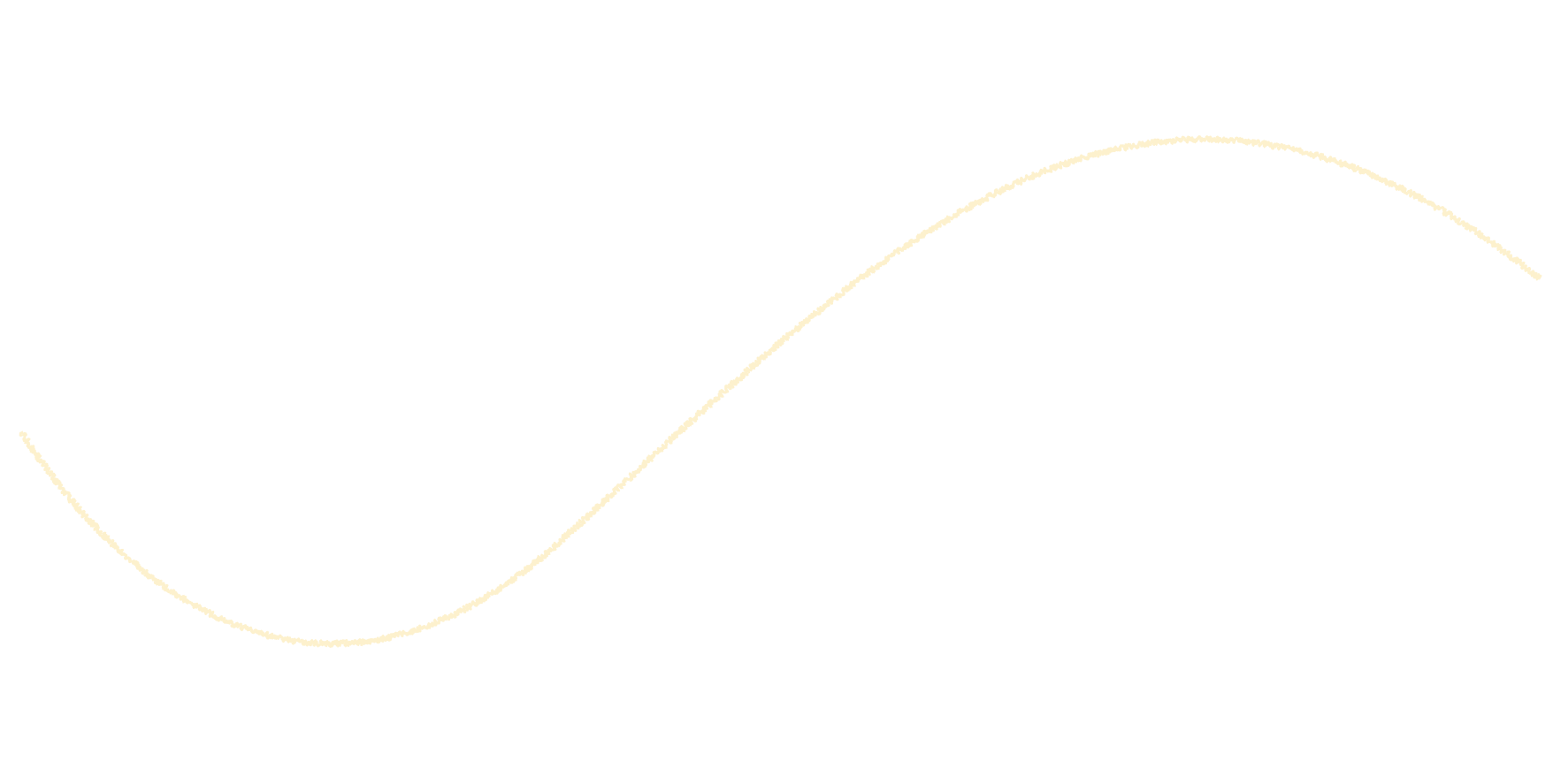
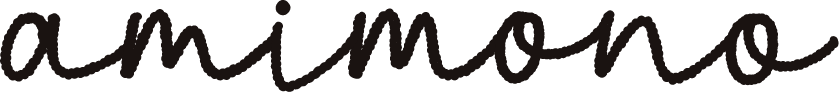



 ポスト
ポスト