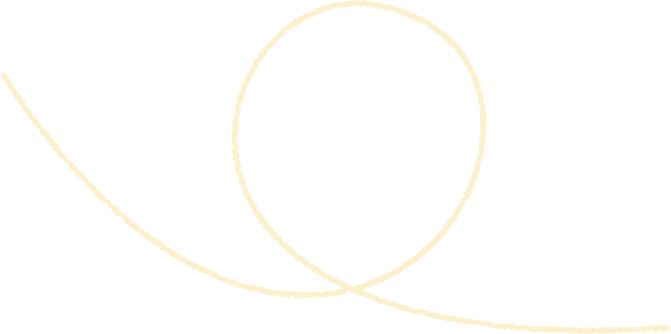
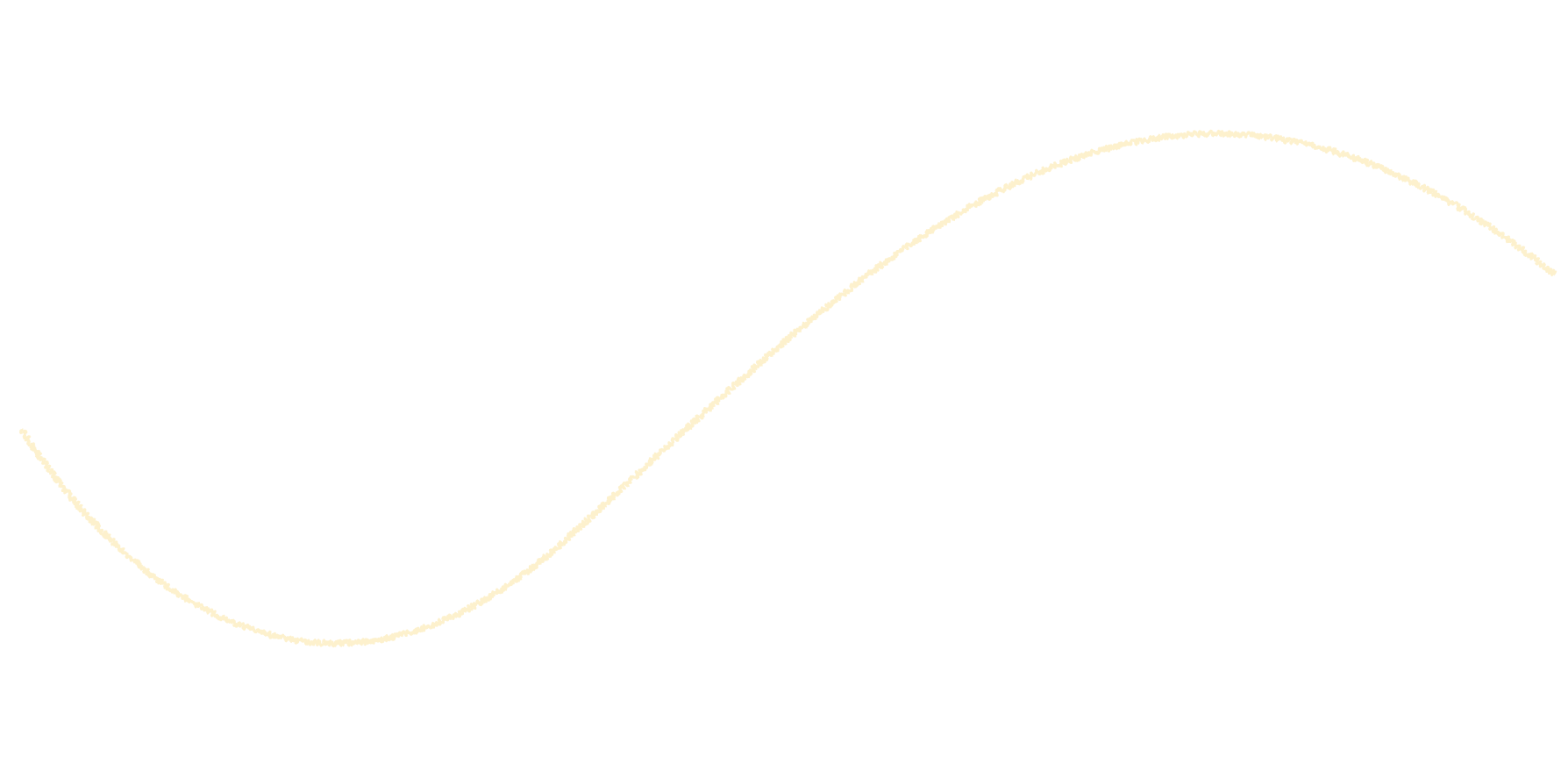
毛糸だま 2018年秋号より
<記事中に出てくる情報は本誌掲載当時のものです。>
ヨーロッパのハートと呼ばれるチェコ共和国は、ヨーロッパのほぼ中央に位置し、1993年、スロヴァキアと分離し誕生した建国25年の新しい国です。
北海道を少し小さくした位の国土に1060万人が暮らしています。四方を山と森に囲まれた国土に点在する、プラハを始めとする古都の間には丘陵がうねり、その間を川が走り、そして国の東南部、古くより栄えたモラヴィアの地には、豊かな田園がどこまでも続いています。チェコ人もまた、日本人同様、自然に心を寄せて暮らしている人たちです。それは伝統工芸、藍染めにも表れています。
 南モラヴィアの田園地帯。肥沃な大地は豊かな実りをもたらし、こうした経済的基盤に支えられたこの地のフォークロアの伝統は多彩で、美しく華やかなものも多く見られます。写真提供:南モラヴィア地方局
南モラヴィアの田園地帯。肥沃な大地は豊かな実りをもたらし、こうした経済的基盤に支えられたこの地のフォークロアの伝統は多彩で、美しく華やかなものも多く見られます。写真提供:南モラヴィア地方局
チェコの藍染めとの出合い
1997年からチェコに4年間滞在し、カレル大学でチェコ語やチェコ美術を学びました。チェコ語はスラブ語のひとつで、文法体系がとても複雑です。そのため習得が難しいと言われる言語で、その文法と格闘していたある日、通学に使っていた路面電車の停留所の近くの仕立屋さんのショーウィンドウに、かつて見たような気がする、紺地に可憐な花模様の生地を見つけました。これが私と藍染めの出合いです。この生地に、かすかにアジアの雰囲気を感じ取り、懐かしさを覚えました。しかし、それがチェコの重要な文化遺産であることを知るのは、もう少し後のことでした。
帰国後しばらくして、藍染めについて調べ始めてわかったことは、現在のチェコで、通年操業を続けているのは、たった2軒の藍染め工房だけであり、熟練した職人の数は非常に限られているということでした。そして、モラヴィアにある2工房の藍染めマイスターが、日本の人間国宝にあたる「民族工芸伝統保持者」の称号をチェコ文化省から授与されたということも知りました。
その一方で、チェコが1989年に自由主義国家となり、経済体制が変化したため、国民には大変な痛みがありました。それをプラハ滞在中に目のあたりにしていたので、藍染め工房が大量生産の風潮から取り残され、存続が大きな問題となるであろうことは、私にも容易に察することができました。こうした状況を知り、まずは人口の多い日本で「チェコの藍染め」を紹介すれば何かの役に立てるかもしれないと考えました。2014年、ヴィオルカを設立し、現在もモラヴィアの工房を定期的に訪問しています。
チェコの藍染めとは
藍染めは古代から広く世界各地で行われてきた、染色技法です。ここで紹介するチェコの藍染めは、欧州で17世紀に確立された型染めの一種で、大航海時代にもたらされたインド藍や防染、ブロック・プリントなどの染色技法が大陸を横断し伝えられたことに始まります。木製あるいは金属製の版木で布地に防染糊を置いたのち、藍の染料槽に布を浸すと、防染した部分の地の色が残り、模様が染め抜かれるというものです。版木を使用することで、ある程度まとまった量を製作できるため、18世紀末から19世紀には、幅広い階層の人々に使われるようになりました。また汚れが目立ちにくいといった実用性から地方にも広まり、チェコ全土においても数多くの藍染め工房が操業していました。
版木は、おもに目の詰まった固い梨の木でできており、大きな文様であれば、木型に直接彫り込み、細かい文様の場合は、木型に真鍮製の鋲(びょう)を打ち込みます。
 木地に鋲を打った長方形の版木は、ヤグルマソウを表しています。民族衣装のスカートの裾飾りの部分に使われるものです
木地に鋲を打った長方形の版木は、ヤグルマソウを表しています。民族衣装のスカートの裾飾りの部分に使われるものです 工房で使われている版木は、長い時間をかけて、木工職人がひとつひとつ手彫りし、鋲を打ち込んだもので、それ自体が工芸品とも言えます。現在も修理や補修をしながら、大切に使われています
工房で使われている版木は、長い時間をかけて、木工職人がひとつひとつ手彫りし、鋲を打ち込んだもので、それ自体が工芸品とも言えます。現在も修理や補修をしながら、大切に使われていますパップと呼ばれる防染糊のおもな材料は、カオリン、アラビアゴム、水です。それぞれの材料の配合量や他に使用される材料は、各工房に伝わる秘法で、長い時間をかけ、マイスターたちの経験によって改良が重ねられてきたものです。材料のひとつ、カオリンは、白磁製造に欠かせない粘土です。チェコから東ドイツを貫くカオリン鉱床群では、良質のカオリンが産出されることで有名で、その証拠にこの地域には、マイセンなどの名窯が点在しています。粘土の主成分であるミネラルを含む防染糊を使うことで、米などの澱粉質を含む防染糊を使う日本の藍染めとは、少し印象が変わります。
白地は白い絵具で塗りつぶしたような純白に、そしてそれに藍色を組み合わせることで、より強いコントラストが生まれるのです。この深い藍色の上に白い模様がきらきらと輝いているような、くっきりとした青と白の対比がチェコの藍染めの個性のひとつと言えるでしょう。手に入りやすい材料を使って作られているということは、まぎれもなく土地の生活に根差している証でもあります。
 防染糊を布地に置く作業をする工房3代めのフランティシェク・ヨフさん。修業を始めた頃は、版木の重さに悩まされたそうですが、とても軽やかに版を押される姿が印象的でした
防染糊を布地に置く作業をする工房3代めのフランティシェク・ヨフさん。修業を始めた頃は、版木の重さに悩まされたそうですが、とても軽やかに版を押される姿が印象的でした
防染糊を置き終わった布は乾燥させ、特殊な金属製の枠に取り付け、藍の染料槽に浸します。5分間浸したら、引き上げて5分間空気にさらし、これを最低5回くり返します。染料のインディゴは、酸化することで、あの鮮やかな藍色になるからです。槽から引き上げた直後の布は黄緑色ですが、次第に青色を帯びてきます。
 布地を乾燥させているところ。手前は染め終わったもの、奥は防染糊を置き終わったもの
布地を乾燥させているところ。手前は染め終わったもの、奥は防染糊を置き終わったもの
また水分を含んだ生地は大変重くなります。ですから一度に染められるのはわずか12メートルほどであり、この長さの生地を染めるのにたっぷり1時間、すべての工程を仕上げるには2〜3週間かかります。布を染める作業は昔から大変な重労働でした。工房での作業を撮影した際、カメラのファインダー越しに一連の作業を見つめているうち、それぞれの工程を進めるマイスターの無駄のない動きの中に、長い時間と経験を凝縮した、たゆみない日々の積み重ねが見えたように思い、感動したことをよく覚えています。
 工房のヤン・ミチカさんが生地を浸す前の染料槽を攪拌しているところ。ミチカさんは若い頃から現在まで、工房における藍染め製作をヨフさんとともに担ってきました
工房のヤン・ミチカさんが生地を浸す前の染料槽を攪拌しているところ。ミチカさんは若い頃から現在まで、工房における藍染め製作をヨフさんとともに担ってきました 藍の染料槽。手前は一度だけ槽に浸けて引き上げたもの、奥は染め上がったもの
藍の染料槽。手前は一度だけ槽に浸けて引き上げたもの、奥は染め上がったもの藍染めのもうひとつの特色は、なんと言っても様々な文様にあり、それぞれの時代様式を反映しています。18世紀に特徴的なものは、人物などのモチーフを組み合わせた具象的な大柄で、ロココ時代の雅宴画を思わせます。「鹿狩り」は、貴族の狩り遊びがテーマで、当時のファッション・リーダーでもあった貴族の暮らしを描写したものです。メインモチーフの鹿と狩人に並んで描かれた庭園の東屋はパゴダと言われる中国風で、当時流行したシノワズリの影響が見られます。
 ☆「鹿狩り」を使ったクッションカバー。長い時間を経て淘汰されてきた優れたパターンは、現在でも変わらぬ魅力を持ち続けています
☆「鹿狩り」を使ったクッションカバー。長い時間を経て淘汰されてきた優れたパターンは、現在でも変わらぬ魅力を持ち続けています
時代が進むにつれ、藍染めの支持体となる布地が手織りの麻布から機械織の軽く平らな綿布になったことで、小花を散りばめた縞模様といった、ビーダーマイヤー様式にならった繊細なものに変化してゆきました。中でも「ローズマリーと野ばら」は、縞状のローズマリーの枝の間に野に咲くばらを配した、大変人気のあったものです。今でもこの模様の生地で作った衣装を、日曜のミサに出かけるために着る地域もあります。
 ☆「ローズマリーと野ばら」を使ったトートバッグ。柄の美しさを引き立て、今の時代に生かす工夫として、フューシャ・ピンクなどの明るい色の裏地を組み合わせています
☆「ローズマリーと野ばら」を使ったトートバッグ。柄の美しさを引き立て、今の時代に生かす工夫として、フューシャ・ピンクなどの明るい色の裏地を組み合わせています
モラヴィアに残る古い藍染めの文様は、野いちご、りんご、麦の穂、パンジー、ヤグルマソウ、鳥や鹿といった自然、あるいは遠い山並みや水車小屋といった身近なモチーフを図案化したものがほとんどで、そのどれもが、自然とともにあり、日常の小さなことに目を留め、愛でる、つつましくも豊かな人々の暮らしを映し出しています。
 ★「鳥と樹」葉の茂った木に鳥を配した生命の樹をモダンにアレンジしたもの
★「鳥と樹」葉の茂った木に鳥を配した生命の樹をモダンにアレンジしたもの ★「ちいさなお庭」庭に実った果実の収穫がテーマ
★「ちいさなお庭」庭に実った果実の収穫がテーマ戦後には、ウールヴ(ÚLUV)という工芸制作団体に属するデザイナーによって制作されたモダン・デザインのパターンが数多くあり、この現代的なパターンもチェコの藍染めの大きな特色です。また、染色法が変わらず、現代まで継続し残っている唯一の伝統的染色技法であることが評価され、2017年3月にユネスコ無形文化遺産登録への申請が行われました。
 ★「チューリップ」花壇に整列したチューリップを図案化したウールヴ時代のモダンなパターンです。濃淡の組み合わせが美しい(写真/森谷則秋)
★「チューリップ」花壇に整列したチューリップを図案化したウールヴ時代のモダンなパターンです。濃淡の組み合わせが美しい(写真/森谷則秋)
ノスタルジックな想い出から現代のファッションへ
藍染め生地は、スカートなどの衣装のほか寝具として生活に取り入れられていました。モラヴィアでは、特に細かな小花模様が好まれ、女性は若い時に仕立てた藍染めの衣装を一生涯、大切に身に着けました。娘時代に自分だけの衣装に使うパターンを選ぶことは、どんなに心躍ることだったでしょう。そして、花嫁は婚礼に際し、婚家に藍染めのカバーをかけた新しい羽根布団を持参しました。
19世紀末には、カラフルな合成染料の普及に押され、工房の廃業が相次ぎました。そして2度の戦争を挟み、共産主義体制が始まると、藍染めの工房は国家に接収され、その製造は前述のウールヴという組織に組み込まれます。そこでは職人と芸術家の共同制作が行われ、同時代の流行も取り入れた新しいデザインが次々と生み出され(写真★)、藍染めは一般の暮らしの中に、贅沢で高品質な素材として再び取り入れられるようになります。
 ★「王様行列」モラヴィア伝統の古い行事をモチーフとしたもの
★「王様行列」モラヴィア伝統の古い行事をモチーフとしたもの ★「ブーケ」19世紀前半のパターンを構成し直した洋風の唐草模様
★「ブーケ」19世紀前半のパターンを構成し直した洋風の唐草模様現在でも、ある一定の年代の女性たちは、子供時代、母親に藍染めのドレスやエプロンを仕立ててもらって着ていたことを懐かしそうに話してくれます。私がプラハのショーウィンドウで見た藍染め生地のある風景は、共産主義時代、藍染めが日常生活に取り入れられていた時の名残だったのです。
 ★「おおきな水滴」を使ったロングジャケット。防染糊を置いた生地を染料槽に一度浸け、さらに糊を置き再び染めたもので、筆者が工房訪問時にウールヴの時代の生地帖から見つけ、再現を提案し実現しました。身体を覆う広い面で使うことで、パターンのユニークさを最大限生かしています(写真/森谷則秋)
★「おおきな水滴」を使ったロングジャケット。防染糊を置いた生地を染料槽に一度浸け、さらに糊を置き再び染めたもので、筆者が工房訪問時にウールヴの時代の生地帖から見つけ、再現を提案し実現しました。身体を覆う広い面で使うことで、パターンのユニークさを最大限生かしています(写真/森谷則秋) ☆「おおきな水滴」を使ったロングジャケット(写真/森谷則秋)
☆「おおきな水滴」を使ったロングジャケット(写真/森谷則秋)自由化後、藍染めの工房は再び持主一族の手に戻りました。最近では、チェコやスロヴァキアのファッション・デザイナーが自らのコレクションに藍染めを取り入れたり、地域の博物館が藍染めの制作を支援したり、また学生たちが工房で制作をしたりと、新しい藍染めのあるべき姿が模索されています。さらに藍染め工房のひとつであるヨフ工房では、一昨年からマイスターの大姪が仕事を継ぎ始め、新しい世代に仕事が手渡され始めています。
 現在のヨフ工房全景
現在のヨフ工房全景 自分で防染糊を置いた布地に加筆をし、整える作業をしている若い後継者ガブリエラ・バルトシュコヴァーさん。ヨフさんの大姪にあたります
自分で防染糊を置いた布地に加筆をし、整える作業をしている若い後継者ガブリエラ・バルトシュコヴァーさん。ヨフさんの大姪にあたりますグローバリゼーションにより均一化されたものが溢れる今だからこそ、多くの地域、民族による手仕事が注目されています。またそれらの手仕事が地域だけでなく、国を超えて広がり、さらに発展してゆくことに期待しています。
現在、私の主宰するヴィオルカでは、伝統あるチェコの藍染めを日本人の視点で見つめ直し、今の時代に生かすことに取り組んでいます(写真☆)。その活動に、日本の人たちが価値を見出し、そしてまたチェコの人たちが、自らの土地の手仕事の持つ価値と可能性を再び発見してくれたなら、これほどうれしいことはありません。
 スロヴァキアの古い生地の柄を復刻した「鹿とザクロ」(写真/森谷則秋)
スロヴァキアの古い生地の柄を復刻した「鹿とザクロ」(写真/森谷則秋) ☆「鹿とザクロ」を使ったタックスカート。現代でも十分に通用する魅力あるパターンであることを再認識させてくれます(写真/森谷則秋)
☆「鹿とザクロ」を使ったタックスカート。現代でも十分に通用する魅力あるパターンであることを再認識させてくれます(写真/森谷則秋)取材・文・現地写真/小川里枝 写真(キャプション文に記載のあるもの)/森谷則秋 編集協力/春日一枝
ヴィオルカ主宰。高崎市美術館が姉妹都市プルゼニュ市の協力で開催した「ボヘミアガラスの100年」展を学芸員として担当し、チェコの芸術・文化に出合う。その後4年間滞在したプラハでは、カレル大学でチェコ語やチェコ美術を学ぶと同時に、各地の美術・博物館や作家を訪ねる。駐日チェコ大使館勤務後、2014年ヴィオルカを設立。藍染めの紹介をはじめとし、チェコの文化や芸術を日本に伝える活動を開始する。美術展カタログの翻訳等にも携わっている。
https://www.violka.jp/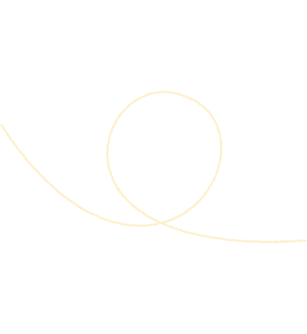
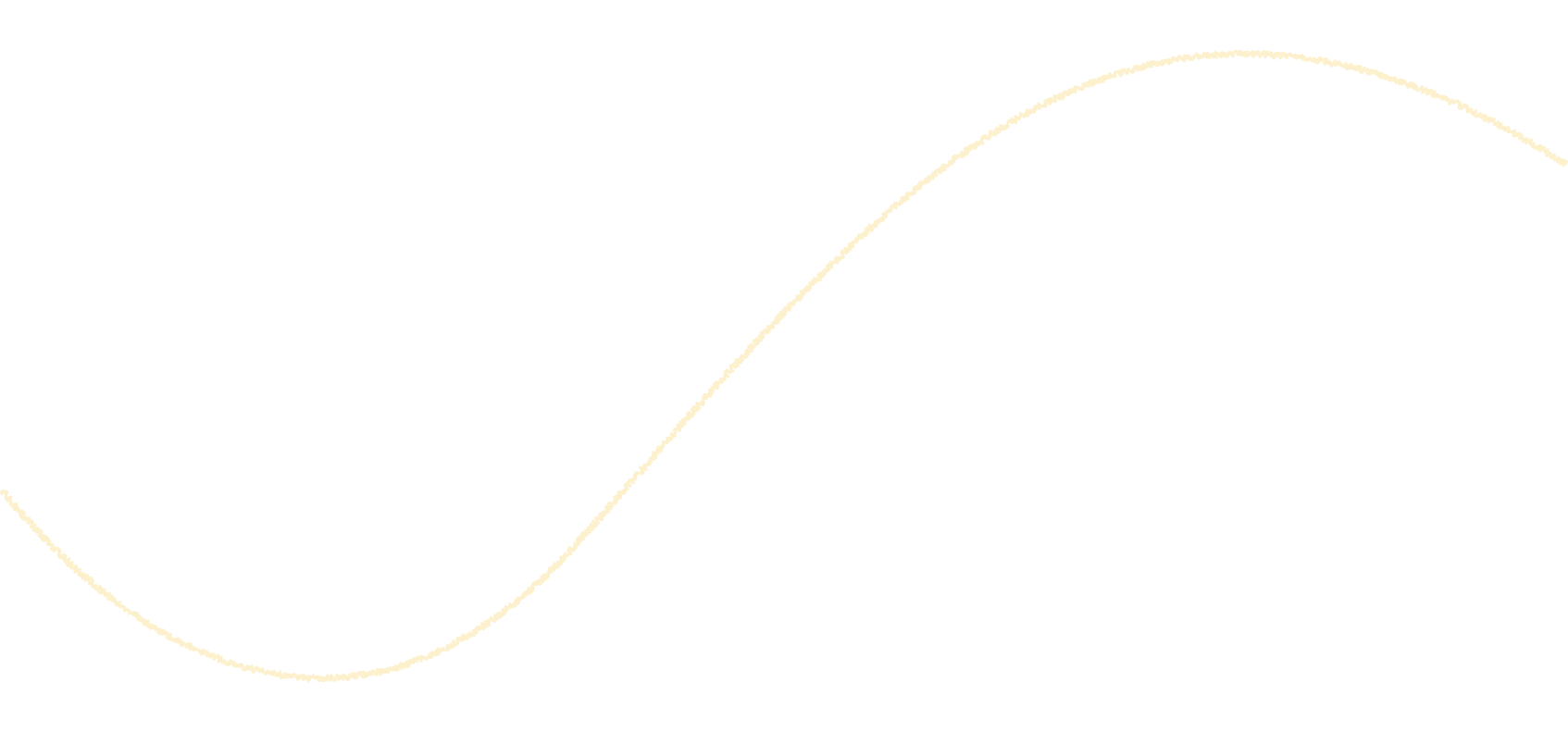
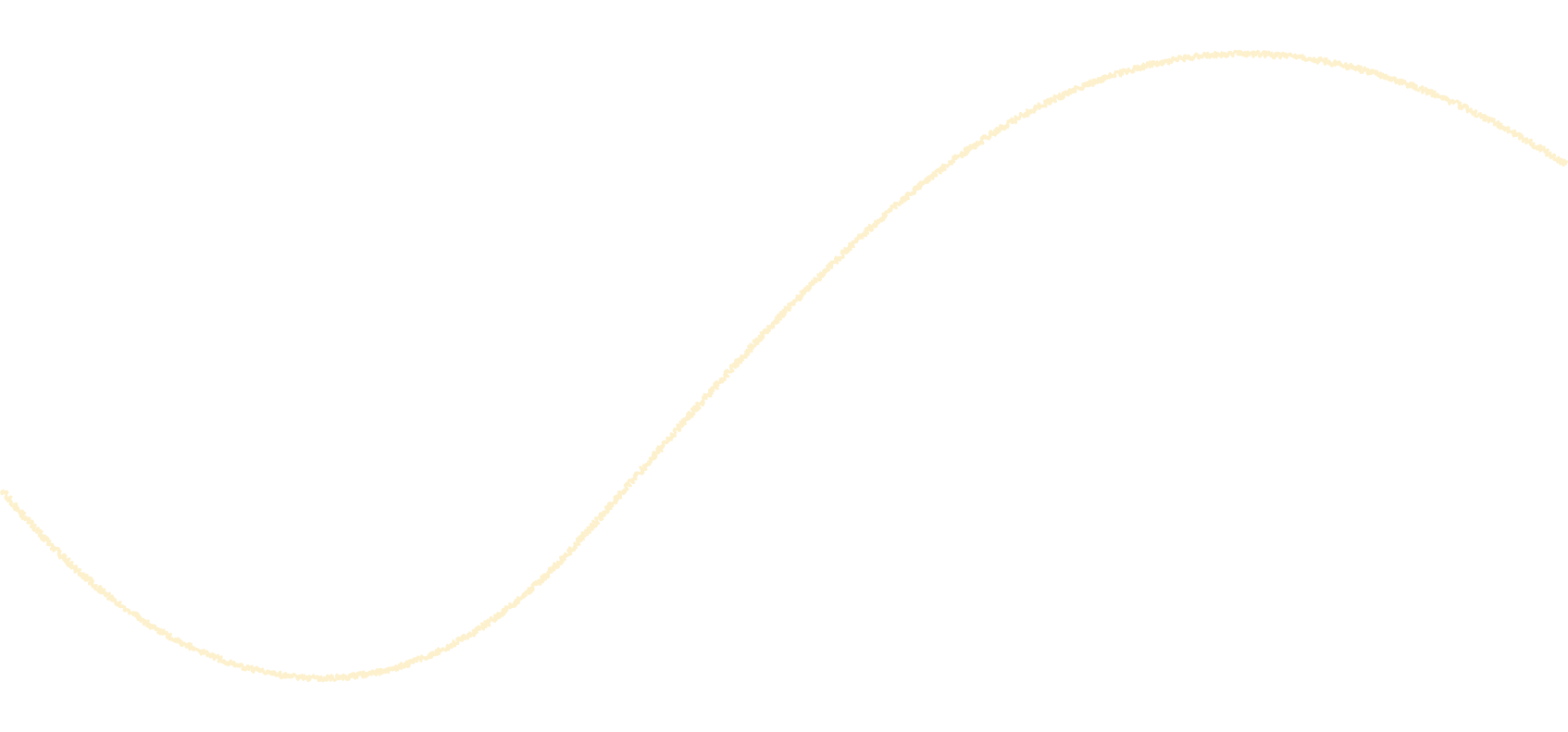
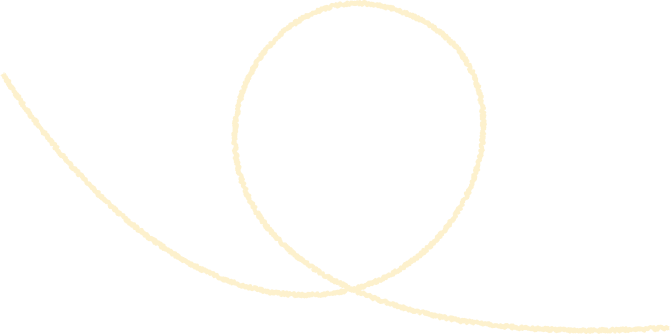
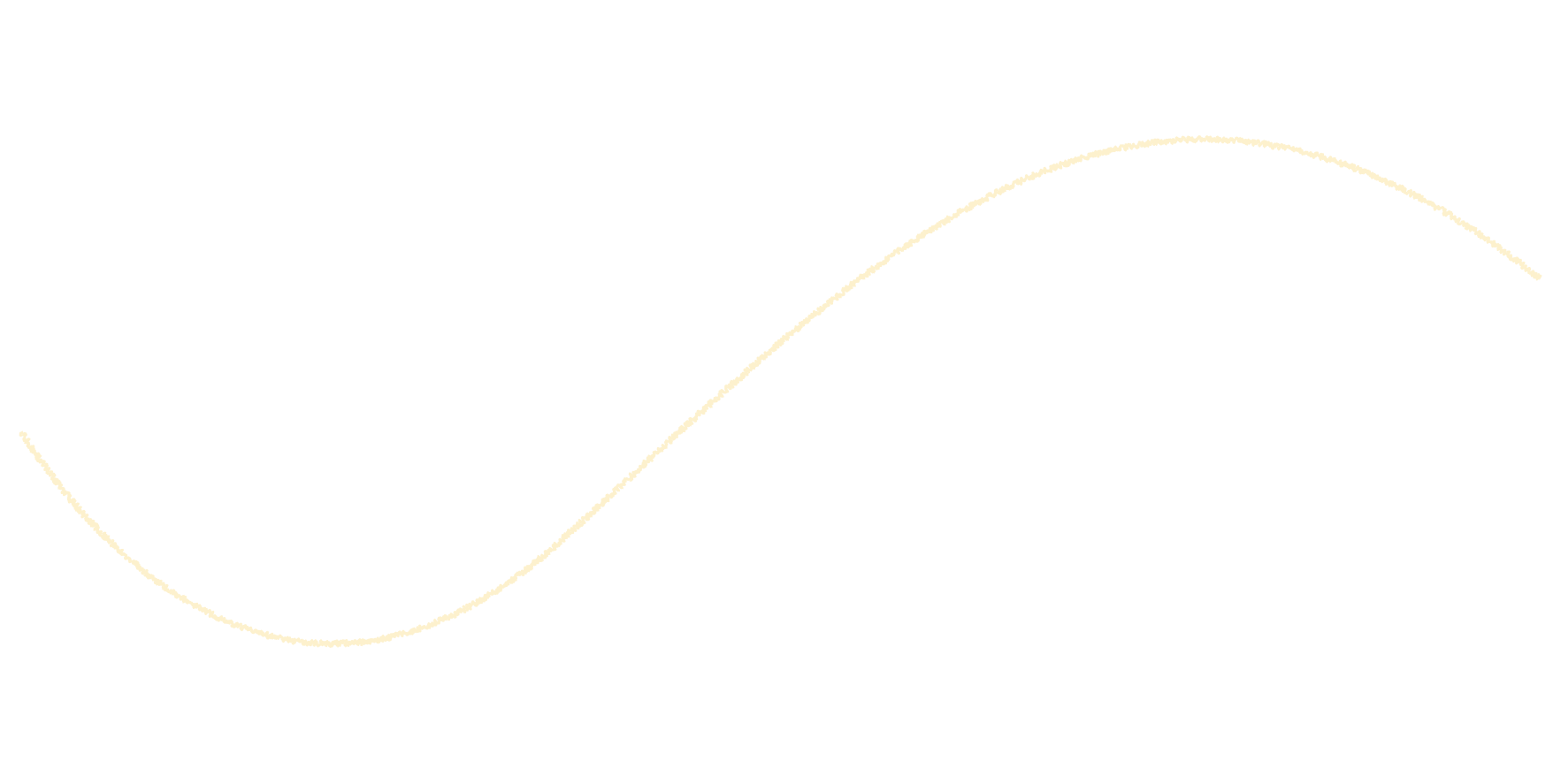
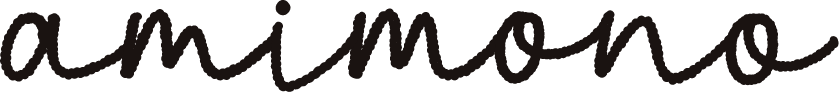



 ポスト
ポスト