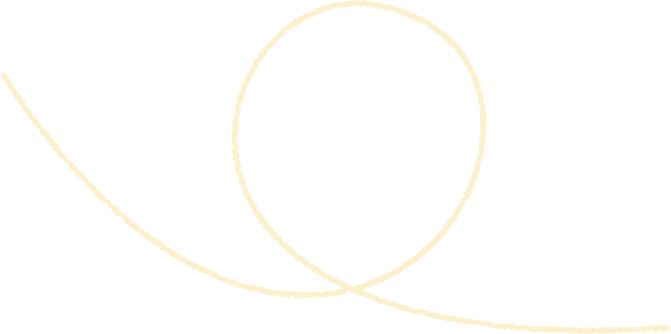
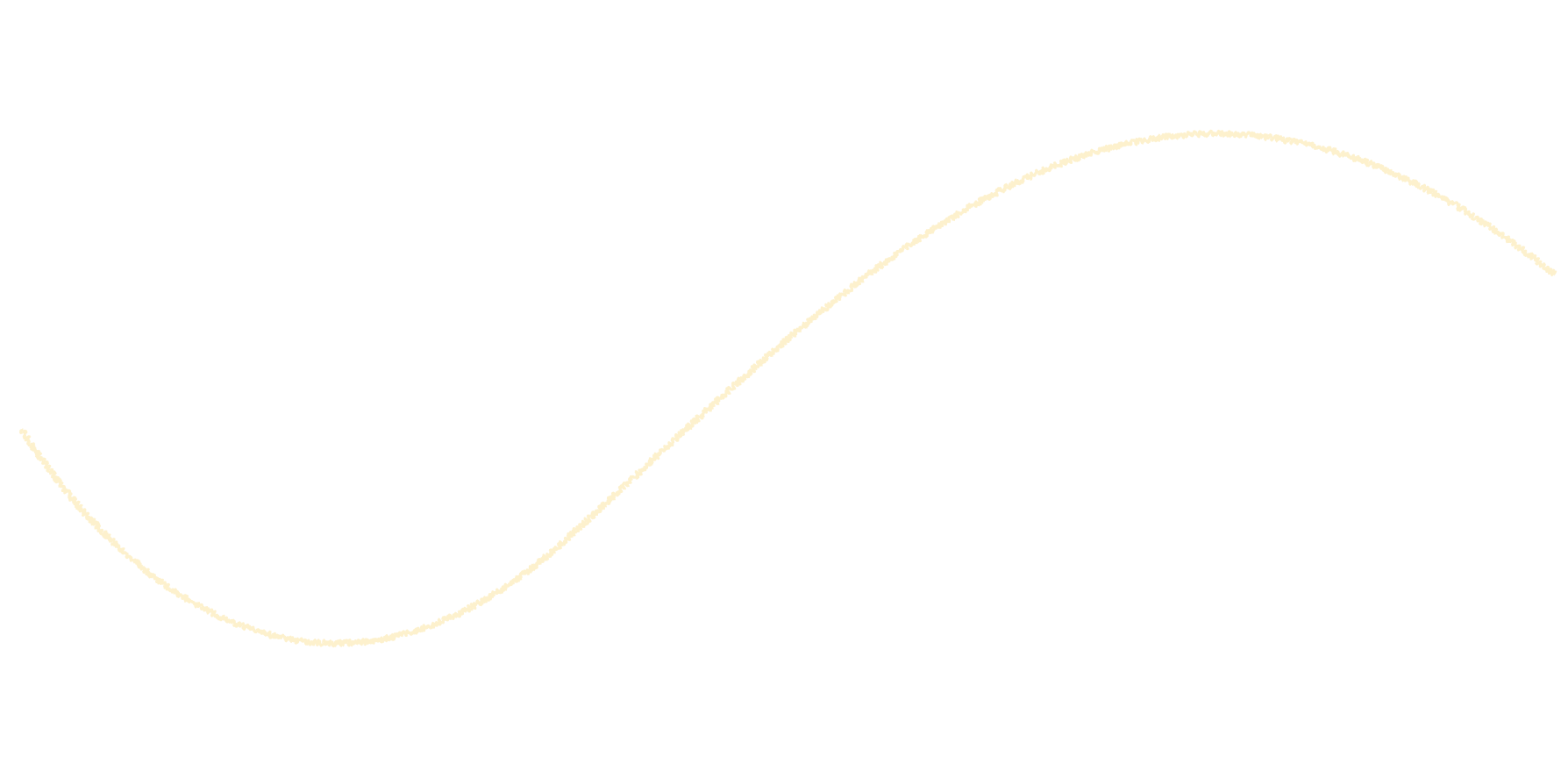
毛糸だま 2018年冬号より
<記事中に出てくる情報は本誌掲載当時のものです。博物館、店舗情報など現在は変更している場合がございます>
オアハカは、メキシコ合衆国で5番めに大きな州で、首都メキシコシティからは飛行機で約50分、長距離バスで約7時間の南東に位置しています。ひとつの州に熱帯雨林、海岸地帯、高原地帯、森林山岳地帯など様々な気候や地形が存在し、16種族以上のインディヘナ(先住民)が暮らしています。それぞれ独自の文化を持ち、多様な手仕事が今も残っています。
オアハカは観光地としても有名な場所なので、観光客へ向けてたくさんの織物や手工芸品が市内のショップに並び、ハイシーズンには展示即売会も盛んに行われます。
 一年を通じて温暖な気候のオアハカ市周辺。テオティトランの教会や村にはブーゲンビリアが咲き誇ってます
一年を通じて温暖な気候のオアハカ市周辺。テオティトランの教会や村にはブーゲンビリアが咲き誇ってます
スペイン人によってもたらされたペダル織りの技術
16世紀にスペイン人がメキシコに来る前のプレイスパニコ時代、オアハカの各地では腰織り(Telar de Cintura)と呼ばれる手法で、綿糸等で織物が織られていました。約480年前にメキシコシティからオアハカへ来たスペイン人が、ペダル織り(Telar de Pedal)と呼ばれる、高機を使った織りの技術や羊を持ち込んだと言われています。
このペダル織りの登場によって、大きく織物の生産方法が変わりましたが、現在でも腰織りを続けている人たちもいます。オアハカ市内から東西南北、車で約7時間から10時間ほど離れた場所に点在している先住民族の各村では、今でも腰織りがメインです。彼らが着用している、ウィピルと呼ばれる貫頭衣などの生産が盛んで、織りも多彩です。これらの地域はオアハカの州都より山奥にあり、歴史的に考えて、スペイン人が持ち込んだペダル織りがここまで浸透しきれていなかったのではないかと思われます。
先住民族の誇りとしての手織り
地域によって様々な気候が存在するオアハカ州では、それぞれの土地で収穫される材料を使い、自分たちのアイデンティティである、先住民族の柄や色を織物に織り込み、身にまといます。
海岸沿いのミステコ族の村では、紫貝やグラナコチニージャで染めた糸や、コユーチェと呼ばれる茶色の綿花を手で紡いだ糸で織ります。
海辺の動植物や風景を織物の柄にしているウヴァ族の村では、昔ながらの腰織りの手法はそのままに、糸は工業製品の綿糸を使います。このほうが精度が高く、かえって先住民族の図案が美しく織れるそうです。
州北部に住むチナンテカ族は、よこ糸をたて糸に差し込み、刺繍のように柄を織り込んでいく、グレッガと呼ばれる手法で織る村もあれば、無地の生地を腰織りで織り上げ、その後刺繍を施している村もあります。
オアハカ市周辺のバジェス・セントラレス地方には、先住民であるサポテコ族が多く暮らし、それぞれ特徴のある織物を織っています。その中で手織りの盛んな3つの村を紹介します。
 ゲラゲッツアの舞踏祭りで披露される、バジェス・セントラレスのサポテコ族の踊りとしても有名なダンサ・デ・ラ・プルマ。サポテコとスペイン人の戦いを表現しています
ゲラゲッツアの舞踏祭りで披露される、バジェス・セントラレスのサポテコ族の踊りとしても有名なダンサ・デ・ラ・プルマ。サポテコとスペイン人の戦いを表現しています
羊毛タペテのテオティトラン
まずは羊毛ラグなどを生産しているテオティトラン・デル・バジェ村(以下テオティトラン)。腰織りによって生活に必要な織物を、綿、絹、イクストレー(マゲイという植物の繊維)の糸を使い、細々と作っていましたが、スペイン人によってもたらされたペダル織りと羊毛を使い、毛布や防寒用の織物を織るようになります。その後1930年代頃から、タペテ(ラグ)と呼ばれる民芸品が各地域に流通するようになり、タペテの生産量が増えました。そのため自分たちで育てていた羊の毛だけでは不足し、オアハカ州のミステカ地方から羊毛を購入するようになりました。また、1900年代初頭に手軽で安価で染められる化学染料が登場し、今まで使われていた自然染料が廃れていきました。
 テオティトランのタペテを織っているところ。複雑な曲線の多い下絵に合わせ、糸を少しずつ織り込みながら作業を進めます。柄にもよりますが、1日8時間の作業で2~3cmしか進まない場合もあるとか
テオティトランのタペテを織っているところ。複雑な曲線の多い下絵に合わせ、糸を少しずつ織り込みながら作業を進めます。柄にもよりますが、1日8時間の作業で2~3cmしか進まない場合もあるとか
そんな中、1960年に自然染料を復活させたいと考えたのが、イサック・バスケスさんです。イサックさんの工房では、自然染料を使って染めた羊毛で織物を織っています。赤にはグラナコチニージャという、プレイスパニコ時代から使われていた染料を使っています。この染料はカイガラムシという昆虫が原料です。サボテンに約3か月とどまり、樹液を摂取したカイガラムシのメスのみを蒸し、乾燥させ、それを挽いて作ります。グラナコチニージャそのものの色は紅色で、ここに酸性のライム汁を加えるとオレンジ系に、アルカリ性の重曹を混ぜると紫系に変色します。この美しい色は「神の血」と呼ばれるほど重宝され、昔はスペイン人と取引きが行われていたそうです。
 イサックさんの工房のトーンの違うグラナコチニージャの糸のみを使って織り上げたタペテ。サポテコ・ダイヤモンドと呼ばれる菱形のデザイン。ダイヤを取り囲むラインの細かい作業にも手が込んでいます
イサックさんの工房のトーンの違うグラナコチニージャの糸のみを使って織り上げたタペテ。サポテコ・ダイヤモンドと呼ばれる菱形のデザイン。ダイヤを取り囲むラインの細かい作業にも手が込んでいます
青には日本でもなじみのある藍、緑には山の岩に繁殖するムスゴという苔、黄色には死者の日に祭壇に飾ることで有名なセンパスチル(マリーゴールド)、黒をさらに漆黒に染めるために、メスキーテという木の実などを使っています。さらに、赤、青、緑、黄色、黒を組み合わせ、何色も必要なだけ表現することが可能だと、イサックさんは言います。
 羊毛を染める自然染料をわかりやすく展示しています。工房を訪問した際にはデモンストレーションを見せてもらうこともできます
羊毛を染める自然染料をわかりやすく展示しています。工房を訪問した際にはデモンストレーションを見せてもらうこともできます
テオティトランは、モンテアルバンやミトラ遺跡に囲まれるような位置にあります。彼らの作るタペテの模様は、遺跡の壁面に施された美しいサポテコのモザイク柄などをモチーフにしている場合と、一枚の絵のような曲線を用いた場合があります。モザイクなどのシンメトリーで幾何学的なデザインは、たて糸を数えながらよこ糸を通していけば表すことができるので下絵は必要ありませんが、曲線のようなデザインは、たて糸の下に図案の下絵をペンで描き写した後に、よこ糸を下絵からはみ出さないように通し、丁寧に時間をかけて仕上げていきます。
 テオティトランのタペテ。Arbol de la vidaと呼ばれる生命の木の小鳥バージョン。単調に見える柄ですが小鳥の羽、目などの曲線部分などを表現するのにかなりの手腕が問われます
テオティトランのタペテ。Arbol de la vidaと呼ばれる生命の木の小鳥バージョン。単調に見える柄ですが小鳥の羽、目などの曲線部分などを表現するのにかなりの手腕が問われます テオティトランの民芸品市場では、様々な柄のタペテが販売されていて、織り手によって作品の風貌が違ってきます
テオティトランの民芸品市場では、様々な柄のタペテが販売されていて、織り手によって作品の風貌が違ってきますテオティトランの博物館の係員に、どのくらいの村人が織りの仕事についているのかと質問したところ、胸を張りながら「ほぼ100%」と言っていたほど、この村では男女問わずに、年配の方から子どもまで織りを習得し、織り上げています。そのことに驚きを隠せません。
 オアハカのペダル織りは立ち作業。写真の織り手はイサックさんの息子ヘロニモさん。糸を染める場合は、そのつど染め上がりが違うので、作品制作中に色が変わらないように、糸は充分な量を一度で染め上げます
オアハカのペダル織りは立ち作業。写真の織り手はイサックさんの息子ヘロニモさん。糸を染める場合は、そのつど染め上がりが違うので、作品制作中に色が変わらないように、糸は充分な量を一度で染め上げます
腰織りとペダル織りが存在するミトラ
テオティトランの東に位置するミトラ村(以下ミトラ)では、現在多くのストールやテーブルクロスやベッドカバーなどの綿織物が生産されています。約60年ほど前に、メキシコ北部のサルティージョ地方から持ち込まれたTELAR DE PEDAL DELANZADERAという、ペダルを使った織機が持ち込まれたことで、ミトラの民芸品としての織物の生産量が増えました。ですが、未だにプレイスパニコ時代の腰織りも続いています。ただし、表と裏の柄が違うミトラ独自の腰織りの技術を持つ職人は、現在では3〜4人ほどしかいないそうです。
 裏と表の柄が違うミトラ織り。写真の色は羊毛が持つそのままの色。たて糸にも羊毛を使い、現在は織り上げた布はポンチョにしたり、テーブルセンターにしたりしています
裏と表の柄が違うミトラ織り。写真の色は羊毛が持つそのままの色。たて糸にも羊毛を使い、現在は織り上げた布はポンチョにしたり、テーブルセンターにしたりしています
今回訪問したミトラの工房では、この貴重な腰織りの技法を見ることができました。この織りはかなりの力を必要とするため、もっぱら男性の仕事だそうです。織り込まれる模様はプレイスパニコ時代に貨幣価値のあったカカオとトウモロコシ、それと欧米人にとっては悪魔の使いですが、サポテコ人にとっては神の使いである蛇が織り込まれています。
 村でもほぼ織り手がいないと言われている、ミトラの腰織りの作業。綜絖(そうこう)部分の仕組みが複雑。アルトゥーロさんの作品はオアハカ市内のテキスタイル博物館でも取り扱い中
村でもほぼ織り手がいないと言われている、ミトラの腰織りの作業。綜絖(そうこう)部分の仕組みが複雑。アルトゥーロさんの作品はオアハカ市内のテキスタイル博物館でも取り扱い中
現在、この工房では腰織りの織物のほか、自然染料で着色した羊毛や綿糸を使い、ペダル織りで織り上げたストールなどを生産しています。グラナコチニージャや藍以外にも、クルミの殻や葉から染めた糸を使っています。優しい色合いのストールは、染色作業の際に羊毛を水で十分に洗うため、完成品は水で洗っても縮むことがなく、洗う回数が増えるたびに優しい肌触りになっていきます。使い込むほどに味の出る、サポテコ族の丁寧な手仕事は一度手にしたら手放せないと、いつも愛おしく感じます。
 アルトゥーロさんの工房で染め上げた優しい色合いの自然染め毛糸。織ってから染める場合もありますが、色がムラになりやすいので、現在は染めた糸から織り上げる方法を優先しています
アルトゥーロさんの工房で染め上げた優しい色合いの自然染め毛糸。織ってから染める場合もありますが、色がムラになりやすいので、現在は染めた糸から織り上げる方法を優先しています
プレイスパニコ時代からの腰織りが続くサント・トマス
サント・トマス・ハリエサ村(以下サント・トマス)は、現在でもプレイスパニコ時代から続く腰織りの方法で、様々な織物を織っています。織り込む柄は100種類近くとも言われていますが、柄の図面は存在しません。小さい頃から織りを始め、代々伝わる織りの技術を受け継ぎ、様々な柄を織り込んでいます。
櫛(Peine)と呼ばれる綜絖も約8種類の幅があり、幅5㎜ほどのものから最長60㎝まで織ることができます。ただ、幅60㎝になると、たて糸を引っ張る力がかなり必要になるため、男性が担当します。
 Finoと呼ばれる、サント・トマスの織りの作業風景。女性たちは毎日の忙しい家事や育児の合間を縫って作業をしています。肉体的疲労を抑えるために、通常は1日2回、朝・晩に分けて2時間から3時間作業をします
Finoと呼ばれる、サント・トマスの織りの作業風景。女性たちは毎日の忙しい家事や育児の合間を縫って作業をしています。肉体的疲労を抑えるために、通常は1日2回、朝・晩に分けて2時間から3時間作業をします
サント・トマスでは、Fajaと呼ばれる紐状の織りをベルトの代わりに使っていました。約40数年前ごろから民芸品を買いにくる観光客や愛好家に向けて、このFajaと長い敷物(テーブルセンターのようなもの)をメインに販売していましたが、売り上げが上がらず、このままでは良くないと生産者たちは感じたそうです。その後自分たちの織った布でMolaと呼ばれる形のバッグやポーチを作り始めました。現在は村の中心地にある民芸品市場で、織りを使ったポーチやバッグ、コースターやランチョンマットなどを観光客向けに販売しています。自分たちの織りを新しい製品開発に導入している熱意はいつもすごいと感心します。
 サント・トマスの商品。ドットやラインを用いてモノトーンにするなど、購買する側の好みも考えて新しい作品を作っています
サント・トマスの商品。ドットやラインを用いてモノトーンにするなど、購買する側の好みも考えて新しい作品を作っています
このような自分たちで商品開発をするという新しい流れの他にも、プレイスパニコ時代に存在した柄の復刻を博物館から依頼され、当時と同じ技法で蘇らせた実績もあります。博物館に保管されている昔の図柄を、現在の生産者が目を数えて読み取り、同じ技法で現代に復活させたのです。ある意味とてもロマンチックです。昔の複雑な柄が現代に蘇ったかと思えば、バッグやポーチなどのお土産品用として、昔にはなかったドットやラインなどの新しい柄も生まれているという話も興味深いです。
 博物館から依頼され、サント・トマスの昔の柄を復刻させた織物。現在村で織っている柄とは頭の部分の冠のデザインや、持っているカゴのデザインなど異なる部分がいくつかあるそう
博物館から依頼され、サント・トマスの昔の柄を復刻させた織物。現在村で織っている柄とは頭の部分の冠のデザインや、持っているカゴのデザインなど異なる部分がいくつかあるそう
サント・トマスの民芸品市場では、お店番をしながらのんびりと腰織り作業を進める女性たちの姿をいつでも見ることができます。
 サント・トマスのFinoと呼ばれる織り。手芸店で売られている縫い糸を使い、5㎜ほどの幅に様々な柄を織り込んでいく。細い糸が入手できるようになり、驚くほど繊細な織りが可能になりました
サント・トマスのFinoと呼ばれる織り。手芸店で売られている縫い糸を使い、5㎜ほどの幅に様々な柄を織り込んでいく。細い糸が入手できるようになり、驚くほど繊細な織りが可能になりました
世界にひとつしかない織物
現在は機械化も進み、昔からある手仕事の多くは機械でも生産できる時代になりました。ですがプレイスパニコ時代から続く祖先の仕事を受け継ぎ、身の回りにある素材を使い、単純に見えながらも計算された織りの手法で、目を見張るほどの素晴らしい手仕事を作り続けている、オアハカの生産者達の技術の高さを尊敬してやみません。
作り手によって織りや色柄が違ってくる世界にひとつしかない織物。「自分達の誇り」として織り上げている作品を、この先も多くの人に知って欲しいと思わずにはいられません。
 カラコル(カタツムリ)と呼ばれる柄は、人が生まれ、育ち、死に、また再生するというサポテコ族の生命の考え方を表しています。使っている羊毛は染めの作業をしていない羊毛独自の色合いをそのまま使用
カラコル(カタツムリ)と呼ばれる柄は、人が生まれ、育ち、死に、また再生するというサポテコ族の生命の考え方を表しています。使っている羊毛は染めの作業をしていない羊毛独自の色合いをそのまま使用
取材・文・現地写真/櫻井陽子 写真/森谷則秋 編集協力/春日一枝
オアハカ在住。さる屋主宰。2006年に単身でオアハカへ渡り就労ビザを取得後、オアハカをメインに民芸品や現地の取材コーディネータなどの仕事に携わり、現在は永住権を取得。著書に「アルテサニアがかわいいメキシコ・オアハカへ」(イカロス出版)がある。
https://saruyaoax.com/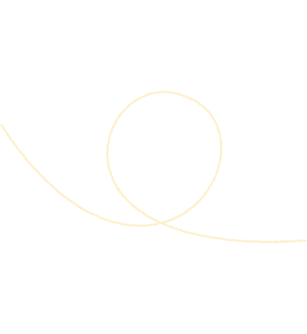
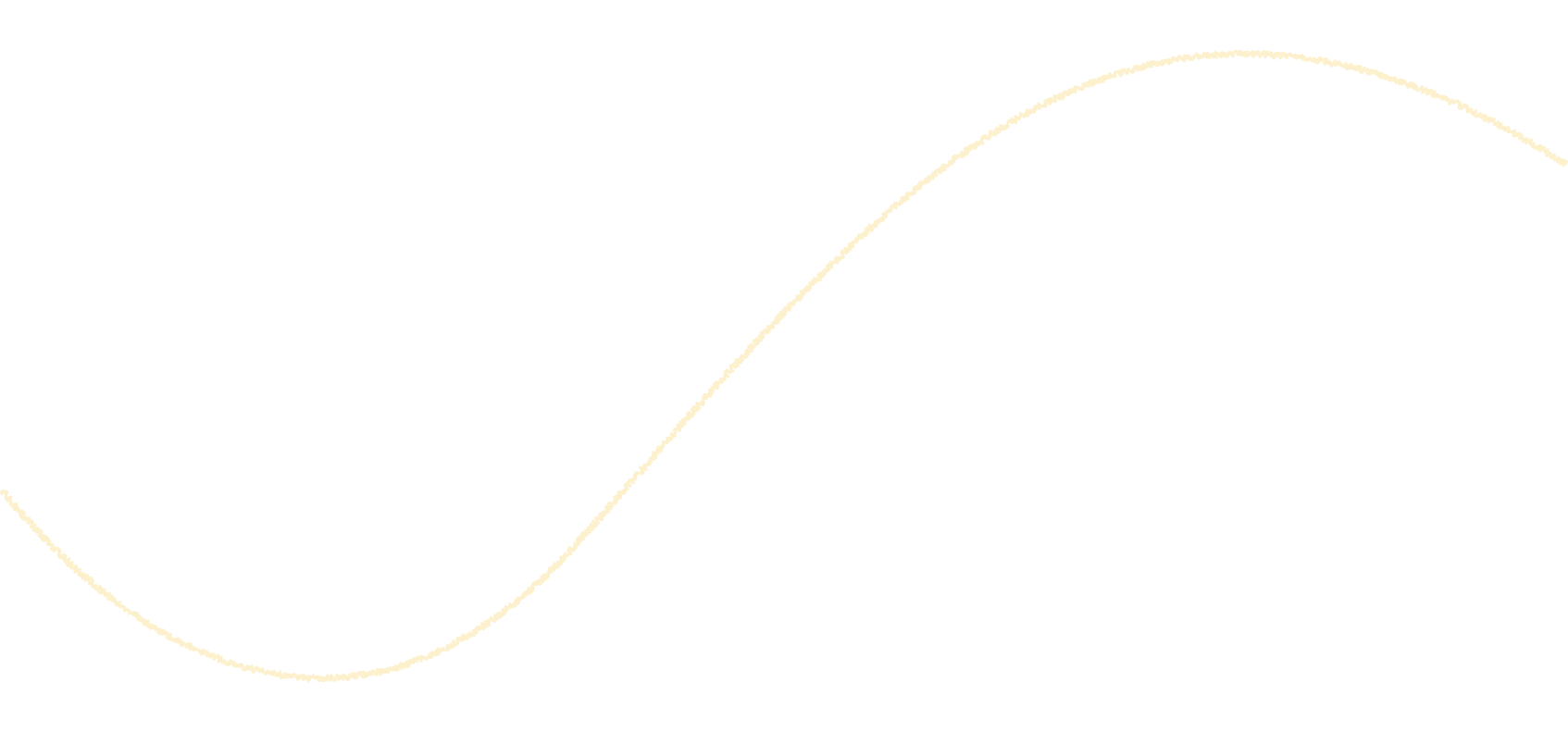
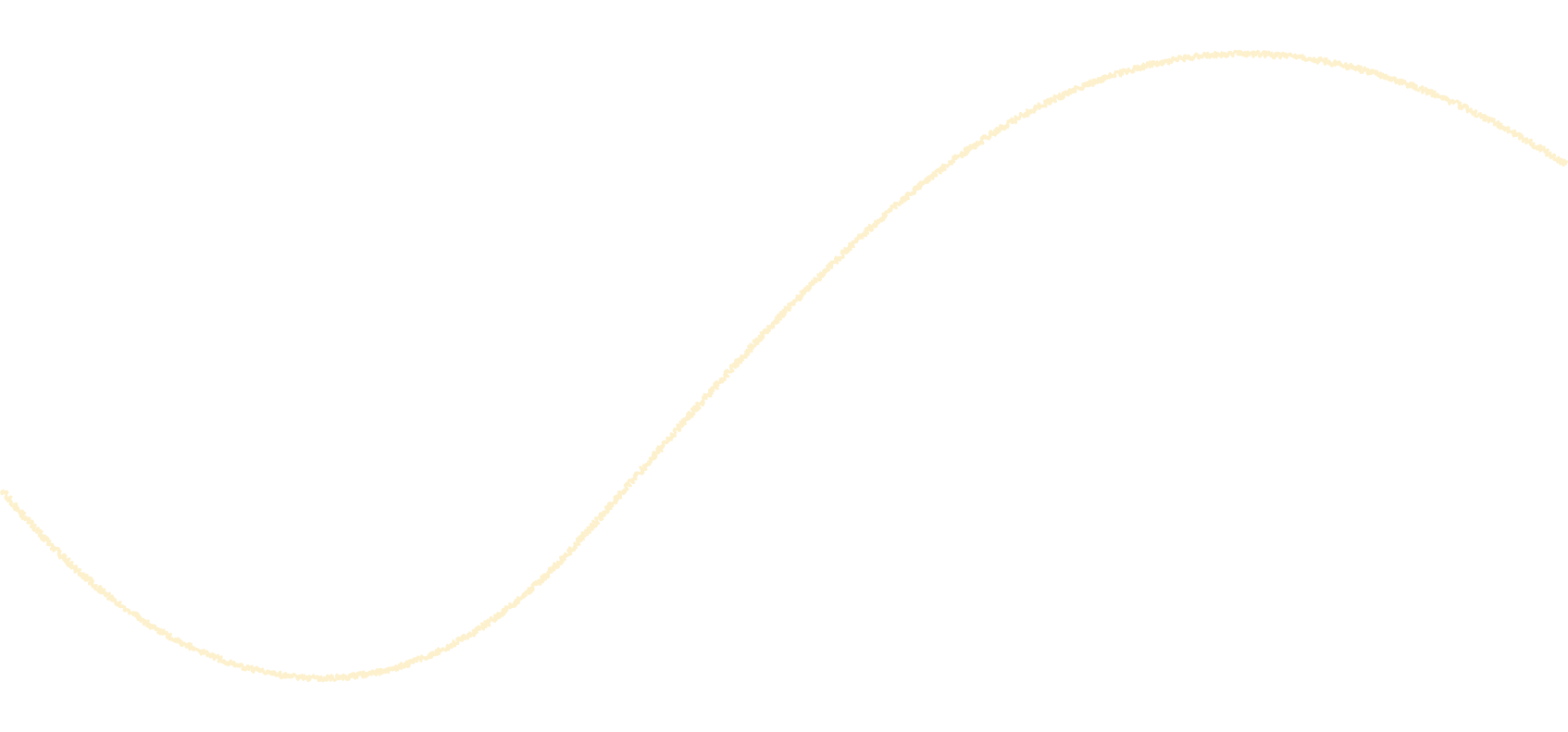
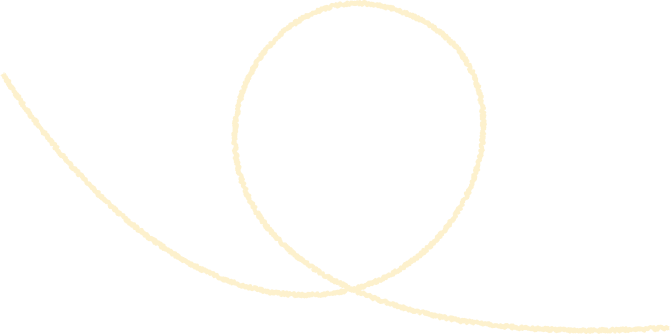
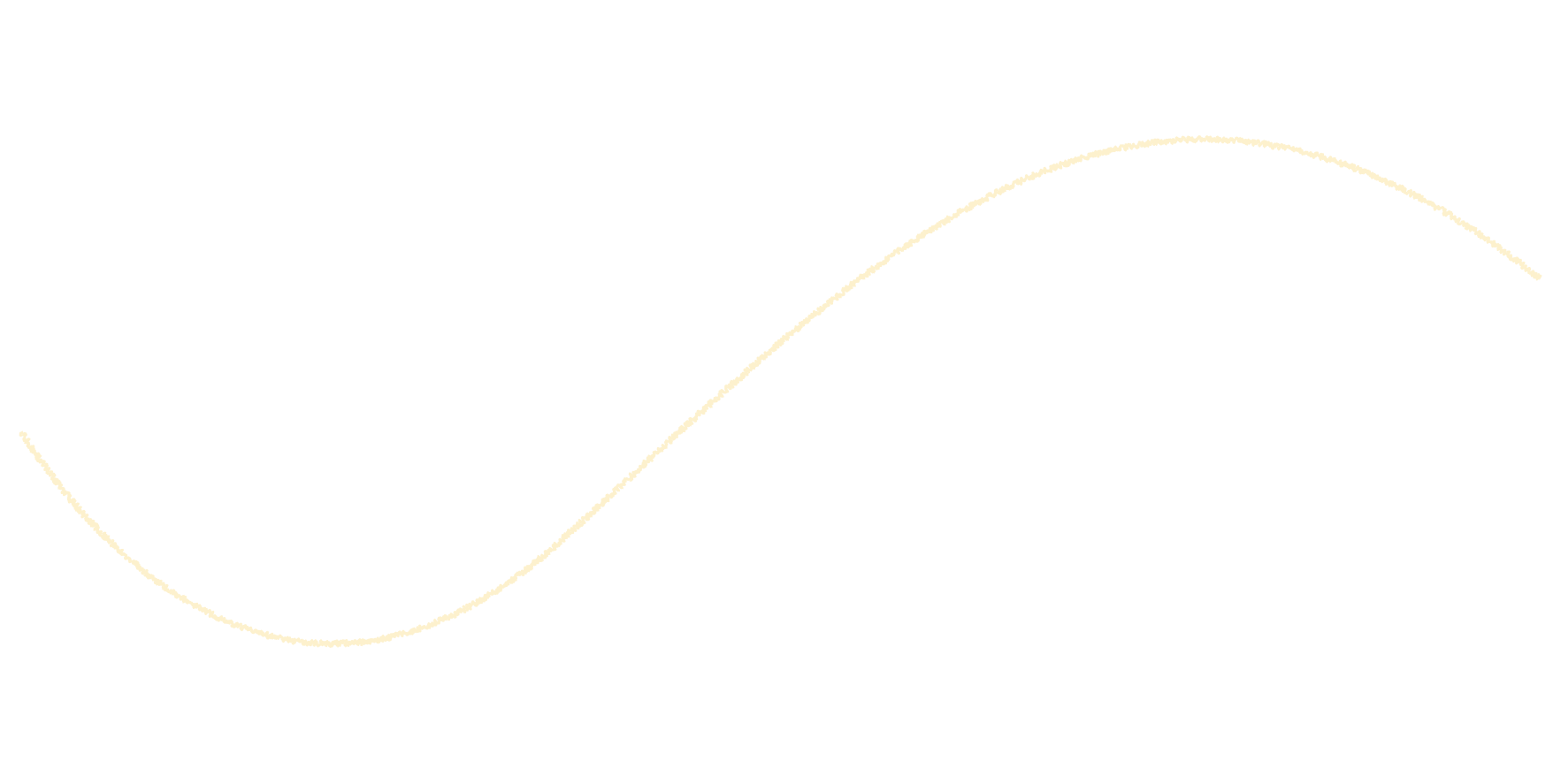
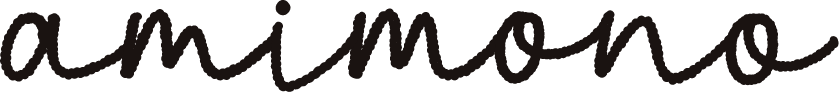



 ポスト
ポスト