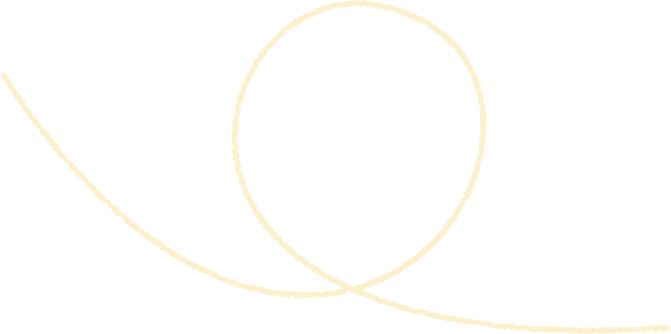
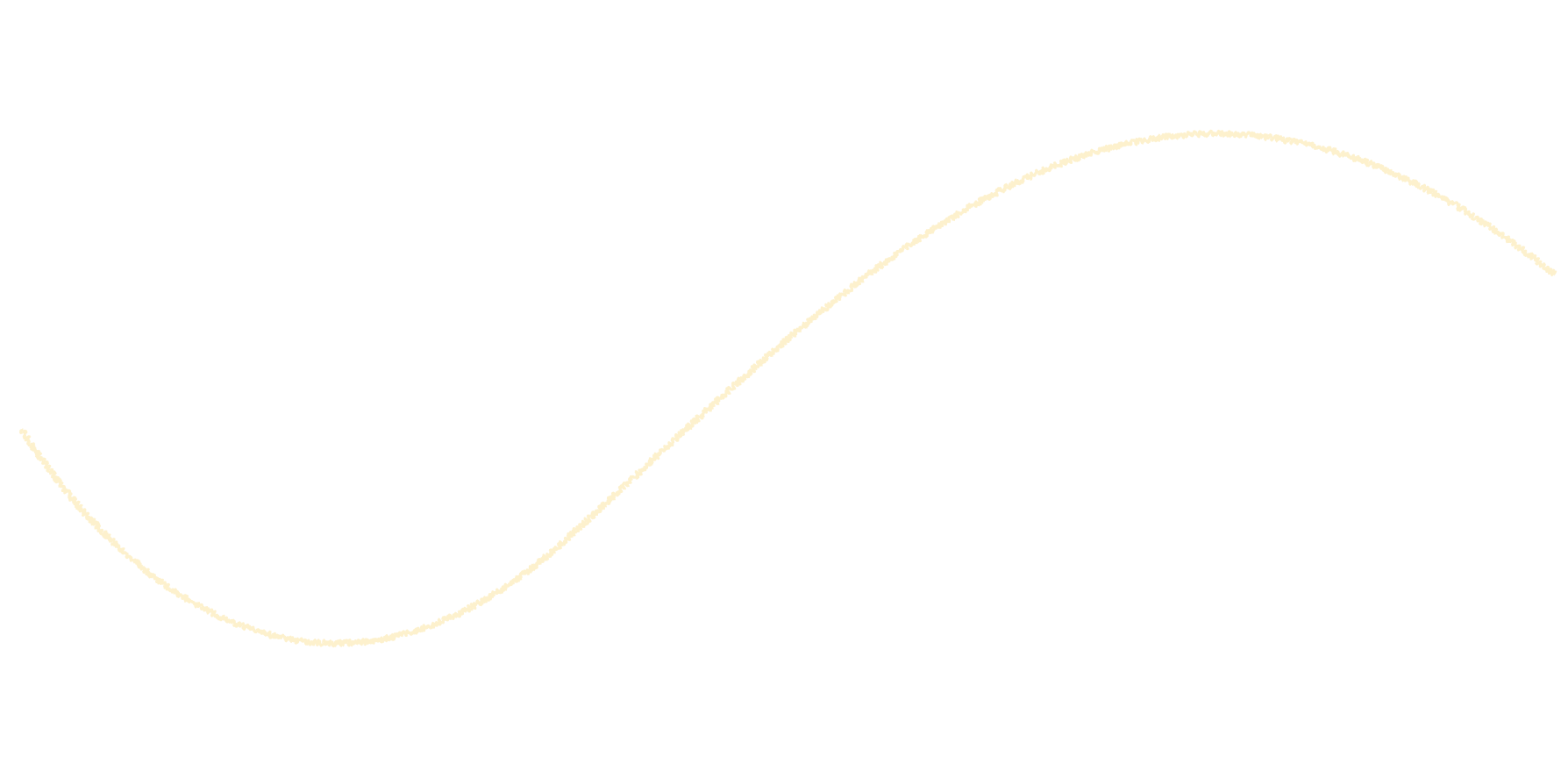
毛糸だま 2020年夏号より
<記事中に出てくる情報は本誌掲載当時のものです。>
ヨーロッパの西の端に位置するポルトガルは、国の大きさが日本の1/4ほどです。大西洋に面し、南北に長い国なので、地域ごとの風土や文化の違いが顕著です。緑豊かな北西部のミーニョ地方は「ポルトガルの庭」とも呼ばれ、華やかな刺繍の民族衣装が有名です。南部のアレンテージョ地方やアルガルヴェ地方は、建物や文化にムーアの影響が色濃く見られます。
 サンタ・クララ修道院の裏手からは、大西洋にそそぐアヴェ川と、旧市街のオレンジ色の瓦屋根が見渡せます。河口近くの浜辺には、現在はホテルになっている16世紀末の美しい星形要塞の、サン・ジョアン要塞が建ちます
サンタ・クララ修道院の裏手からは、大西洋にそそぐアヴェ川と、旧市街のオレンジ色の瓦屋根が見渡せます。河口近くの浜辺には、現在はホテルになっている16世紀末の美しい星形要塞の、サン・ジョアン要塞が建ちます
15世紀から17世紀にかけての大航海時代は、ポルトガル史上できわめて重要な時代です。アフリカ大陸やインド洋の諸国、そしてブラジルとの貿易や植民活動によって、莫大な富や産物、文化が国にもたらされました。マヌエル1世(1469年〜1521年)の治世の時代には、マヌエル様式というポルトガル独自の美術と建築の装飾様式が流行しました。海藻や珊瑚やロープといった海や航海に関するものや、貿易で訪れた異国の動植物などをモチーフにして、修道院の回廊や、建物の窓やドアのまわりなどを、重厚で華やかな彫刻で飾りました。首都のリスボンには、マヌエル様式で建てられた、ジェロニモス修道院やベレンの塔など、大航海時代を象徴する歴史的建造物が建ちます。
ポルトガル各地に伝わるレース
ポルトガルは手仕事も盛んで、様々な種類のレースが各地に伝わります。北部のフェルゲイラという町には、フィレというレースがあります。これは、漁網を編む要領で作ったネットを四角い木枠に張り、編み目の間を針と糸でかがって模様を作るものです。ベッドカバーのようなサイズのものになると、数人がかりで大きな木枠を囲んで作ることもあります。
「レンダシェ・デ・ビレルシェ」こと、ボビンレースも古くからポルトガルに伝わっています。ボビンレースの織り方は、ピロー(クッサンとも)と呼ばれる織り台の上に型紙を固定し、ボビンに巻いた何本もの糸を、型紙の始点に打ったピンに固定した状態で織り始めます。型紙のデザインに従って、要所ごとにピンで固定しながら、平織りと綾織りの2種類の糸運びで織っていきます。
ピローには、大きく分けて、円筒形のロールピローと、平らな四角形や円形のフラットピローの2種類があります。ロールピローは回転しながら使うので、細長いレースを織るには便利な形です。糸を巻くボビンは、持ち手の部分にふくらみのある細長い棒ですが、国によっていろいろな形があります。
 貝殻やお花のモチーフ、記念の物らしいシャンパンのコルクの栓、といったものを、ボビンが転がらないように止めておくためのピンの頭に使っています
貝殻やお花のモチーフ、記念の物らしいシャンパンのコルクの栓、といったものを、ボビンが転がらないように止めておくためのピンの頭に使っています
レース用の糸は綿と麻が一般的ですが、絹糸も売られています。糸には2/60や2/120などの番号が表示されていますが、2/60の場合、60は糸の番手を、2は糸の撚りの本数を表し、番手の数字が大きいほど糸は細くなります。アンティークのレースの中には非常に細い麻糸が使われたものもありますが、切れやすいので織るには細心の注意が必要でした。しかし、現在はそこまで細い糸は製造されていません。
かつて、ポルトガルのボビンレースは、北西部沿岸のヴィアナ・ド・カステロ、内陸部のニザ、リスボン近郊のセトゥーバル、南部沿岸のシルヴェスなどでも作られていましたが、現在は産業として成り立つほどではありません。リスボン近郊の小さな漁師町のペニシェでは、レースの伝統を保持する活動に力を入れています。海沿いの街らしく、ここで作られるレースは、魚や貝といった、海に関するモチーフの作品が見られるのが特徴のひとつです。町には小さいながらも充実した展示をするレースの博物館があり、レース学校も運営されています。
 ペニシェの町に1軒あるレース店のショーウィンドウには、民芸品の漁船の模型とともに、レースの敷物が飾ってあります
ペニシェの町に1軒あるレース店のショーウィンドウには、民芸品の漁船の模型とともに、レースの敷物が飾ってあります
生活の糧として作られたヴィラ・ド・コンデのボビンレース
ポルトガルでボビンレースが最も盛んな町は、ミーニョ地方のヴィラ・ド・コンデです。ヴィラ・ド・コンデは、ポルトガル第二の都市であるポルトから、北へ約25kmの海沿いに位置します。歴史ある町で、大航海時代の16世紀には、造船業の中心地として栄えました。旧市街のそばを流れるアヴェ川のほとりには、18世紀に改修された壮大なサンタ・クララ修道院が建ち、その背後には、ポルトガルで二番めに大きいと言われる1714年に作られた全長約7㎞の水道橋があります。修道院の建つ丘から隣町へ、ゆるやかなカーブを描きながら続く水道橋は絵になる美しさです。
旧市街には石造りの古い家が立ち並び、お菓子屋さんでは修道院伝来のお菓子が売られています。ビーチにも近く、夏になると近隣からの海水浴客で賑わいます。観光には良い町ですが、認知度はそれほど高くないようで、観光客の姿はまばらです。しかし、その分ゆっくりと街歩きを楽しむことができます。
ヴィラ・ド・コンデにいつボビンレースが伝わったのかははっきりしませんが、船員と商人によって北ヨーロッパから伝わり、16世紀にはすでに組織的な製造がされていました。この時代はブラジルへ多くの出稼ぎ労働者が渡った時代でもあり、レースを作るのは家に残った女性が食べていくための大切な仕事でした。ポルトガルでは昔から「女性には3つの仕事がある」とされ、それは「家事」と「夫の相手」、そしてヴィラ・ド・コンデの場合は「レース」だと冗談めかして言われます。また、両親が出稼ぎに行ってしまった家では、子供だけでも生活していくためにレースを作らなくてはいけませんでした。ですから、女性たちは4〜5歳になると母親から習ったり、修道院に通ったりしてレースを学び、高齢になってもレースを作り続けました。
 1958年にマリア・アイレスさんが織った「4つの巻貝」と名付けられた、大きめの花瓶敷き。800本のボビンを使って、200番手というごく細い麻糸で織っています。中央には十字架の形に海藻が、まわりには8匹の魚が泳いでいる、海辺の町らしいデザイン
1958年にマリア・アイレスさんが織った「4つの巻貝」と名付けられた、大きめの花瓶敷き。800本のボビンを使って、200番手というごく細い麻糸で織っています。中央には十字架の形に海藻が、まわりには8匹の魚が泳いでいる、海辺の町らしいデザイン 海のモチーフがデザインされた、教会のミサで頭にかぶるベール。ヒトデや海藻、クラゲやホタテ貝といった海のモチーフが散りばめられています
海のモチーフがデザインされた、教会のミサで頭にかぶるベール。ヒトデや海藻、クラゲやホタテ貝といった海のモチーフが散りばめられています富裕層に愛された贅沢なレース
ヴィラ・ド・コンデのボビンレースに使われる道具は、藁か綿の詰まったロールピロー(アルモファダ)と、ミーニョ地方のヴィアナ・ド・カステロの工場で作られている木製のボビン(ビレルシェ)です。糸は、16世紀に伝わった当初は麻が使用され、後に綿が使われました。現在はハンガリーやドイツなどで作られる木綿糸、そしてイギリスとポルトガルで作られる麻糸が使われます。
デザインは海沿いの田舎町らしく、魚や貝、帆船といった海に関するものと、花に関するものに特徴があり、「コンシーニャ(貝)」や「エスカマシェ(うろこ)」といった、町特有の名前で呼ばれるステッチが多数あります。職人は顧客から注文を受けると、昔から伝わる数多くの図案の中から選んでレースを織ります。
ジョアン5世の時代の1749年〜1751年の3年間、レースは贅沢すぎるということで製造禁止令が出され、その間食い扶持を失った職人たちは非常に困りました。しかし、ジョアンが亡くなり、ジョゼ1世に代替わりすると再び製造は許可されました。レースの製造のピークは17世紀〜18世紀で、富裕層向けの高級なベッドリネンやテーブルリネンなどの身の回り品や装飾品、教会の祭壇を飾るレースや司祭の衣服を飾る衿、洗礼用の布といった宗教用品が作られ、それらは全て国内からの注文で、輸出はされませんでした。
19世紀から20世紀の初頭、町には缶詰やテキスタイルなどの工場ができ、多くの女性が働きに出るようになりました。そして、1919年にはレースの専門学校が創立され、母親たちが工場勤めをしている日中、少女たちは学校でレースを学びました。
レース学校は今も活動を続けていて、授業は週に5日あり、現在は職人の先生が一人で30人の生徒を教えています。入学すると、最初は4個か6個のボビンを使った簡単なステッチから始め、より複雑な組み合わせに進んでいきます。一人前になるには相当の練習が必要ですが、例えば5歳で入学した子供は、18歳になる頃には良い収入が得られるくらいに上達します。現在のヴィラ・ド・コンデではレースを織る人は200人ほどおり、そのうちの30人ほどはプロの職人として活動しています。
 レース学校では、大人に混じって小さな子供も作業をしています。6歳くらいになると、課題であるリボンの形をしたレースも織れるようになります
レース学校では、大人に混じって小さな子供も作業をしています。6歳くらいになると、課題であるリボンの形をしたレースも織れるようになります
伝統のレースを受け継ぐ人たち
64歳のアリス・ヴェイガさんもそうしたプロの職人の一人で、仕事のために5歳からレースを学びました。ハンカチや衿、宗教用品やテーブルクロスなどを、デザインの複雑さにもよりますが、1日8時間ほどの作業時間で、1年で10点くらい織るそうです。アリスさんは職人の中でも特に優れた技量があり、今までにウェディングドレスとベールも10組ほど手がけました。
アリスさんは「ボビンレースは収入を得るために始めたものですが、私は本当にこの仕事が好き」なのだと言います。ちなみに、数人の職人に聞いた話では、自分のためにレースを織ることは少なく、クリスマス用の飾りや、自分の結婚式や子供の洗礼式で使ったものなど、自宅には数えるほどのものしかないそうです。
 ヴィラ・ド・コンデの博物館に展示されている、ポルトガル人にとって非常に大切な赤ん坊の洗礼式に使われるレースの衣装小物
ヴィラ・ド・コンデの博物館に展示されている、ポルトガル人にとって非常に大切な赤ん坊の洗礼式に使われるレースの衣装小物
町の市場でレースの店を構える49歳のマリア・サラザールさんは3歳からレースを学び、店の経営のほかに、職業訓練所で失業中の女性たちに織り方も教えています。マリアさんの祖母はレース学校の初代の教師で、母親も同じく教師でした。マリアさんは大学でジャーナリズムの学位を取得し、ジャーナリストとしてラジオ局で働いていましたが、2011年にラジオ局は閉鎖となりました。
失業したマリアさんは途方に暮れましたが、レースの店を開くことを思いつき、「100年以上昔から伝わる町の伝統工芸であり、高貴な芸術品であるボビンレースの探求をしていこう。そしてデザインに新しさも取り入れ、レースに革新をもたらそう」と考えました。この取り組みは成功し、店には伝統的なレースのほかにも、家具やファッションなどに使うレースの注文が、個人やデザイナーや企業から入るようになりました。中でもアクセサリーの需要は特に多いそうです。
 ヴィラ・ド・コンデの市場にある、マリア・サラザールさんのレース店「レンダシェ・デ・セウ」。店では実演をしながら、アクセサリーやドイリーといった小物が売られています
ヴィラ・ド・コンデの市場にある、マリア・サラザールさんのレース店「レンダシェ・デ・セウ」。店では実演をしながら、アクセサリーやドイリーといった小物が売られています
ヴィラ・ド・コンデのレース博物館には、町で作られた20世紀初頭からのレースのコレクションや、世界各国の道具などが展示されています。
 「バラとヒヤシンス」と名付けられた、花瓶敷きほどの大きさの作品
「バラとヒヤシンス」と名付けられた、花瓶敷きほどの大きさの作品 「セビリア風」と名付けられた、教会のミサのときに頭にかぶるベール
「セビリア風」と名付けられた、教会のミサのときに頭にかぶるベール建物は17世紀初頭に建てられた貴族の館を利用し、館内にあるレース学校では生徒や職人の実演も見ることができます。
 ヴィラ・ド・コンデの博物館にあるレース学校で、生徒がレースを織っているところ。熟練者ともなると作っているものも、課題というより、注文品を織ることの方が多いよう
ヴィラ・ド・コンデの博物館にあるレース学校で、生徒がレースを織っているところ。熟練者ともなると作っているものも、課題というより、注文品を織ることの方が多いよう ロールピローに置かれた型紙には、下絵が見えないほどピンがびっしりと打たれています
ロールピローに置かれた型紙には、下絵が見えないほどピンがびっしりと打たれています館内にはイベントで町の職人や生徒たちが作った、ハンカチほどの大きさのレースをつなげた大作が飾られています。ギネス記録にも認定された自慢の作品ですが、この町の人々はこれからもこんなふうに力を合わせ、ボビンレースの伝統を守っていくのでしょう。
 博物館の中には、ギネス記録になったレースが飾られています。2015年に、大人から子供まで、150人のレース職人と製作者が、8kg の綿糸を使い、全てデザインの違う30cm四方のモチーフを437枚織り、ボビンレースでつなげて1枚の巨大なレースに仕立てました
博物館の中には、ギネス記録になったレースが飾られています。2015年に、大人から子供まで、150人のレース職人と製作者が、8kg の綿糸を使い、全てデザインの違う30cm四方のモチーフを437枚織り、ボビンレースでつなげて1枚の巨大なレースに仕立てました 博物館が所蔵する一番古い作品で、1933年にルイ・ヴァスさんによってデザインされ、学校の生徒であるアルビナ・モンテイロさんによって織られたカーテン。鉢からあふれんばかりに咲く花々と、鳥が描かれ、アール・デコ様式の雰囲気も感じさせます
博物館が所蔵する一番古い作品で、1933年にルイ・ヴァスさんによってデザインされ、学校の生徒であるアルビナ・モンテイロさんによって織られたカーテン。鉢からあふれんばかりに咲く花々と、鳥が描かれ、アール・デコ様式の雰囲気も感じさせます マリア・モンテイロさんの作品。900本のボビンを使って、中心に4枚、まわりに8枚の扇を配して織られた優雅な作品。マカオなど、海外の展覧会でも展示されました
マリア・モンテイロさんの作品。900本のボビンを使って、中心に4枚、まわりに8枚の扇を配して織られた優雅な作品。マカオなど、海外の展覧会でも展示されました 1944年にマリア・クルスさんによって織られた、教会の祭壇の飾り。2m以上の長さがある大作
1944年にマリア・クルスさんによって織られた、教会の祭壇の飾り。2m以上の長さがある大作取材・文・写真/矢野有貴見 編集協力/春日一枝
文化服装学院アパレルデザイン科卒業。和装品のデザイン、古美術店の勤務を経て、Webやイベントなどでポルトガル民芸店「アンドリーニャ」を運営。『レトロな旅時間 ポルトガルへ』(イカロス出版)『持ち帰りたいポルトガル』(誠文堂新光社)『ポルトガル名建築さんぽ』(エクスナレッジ)などがある
http://www.olaportugal.net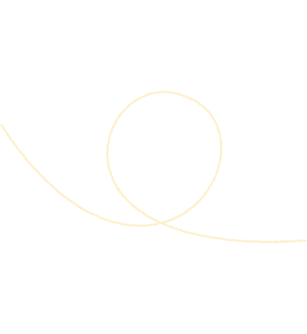
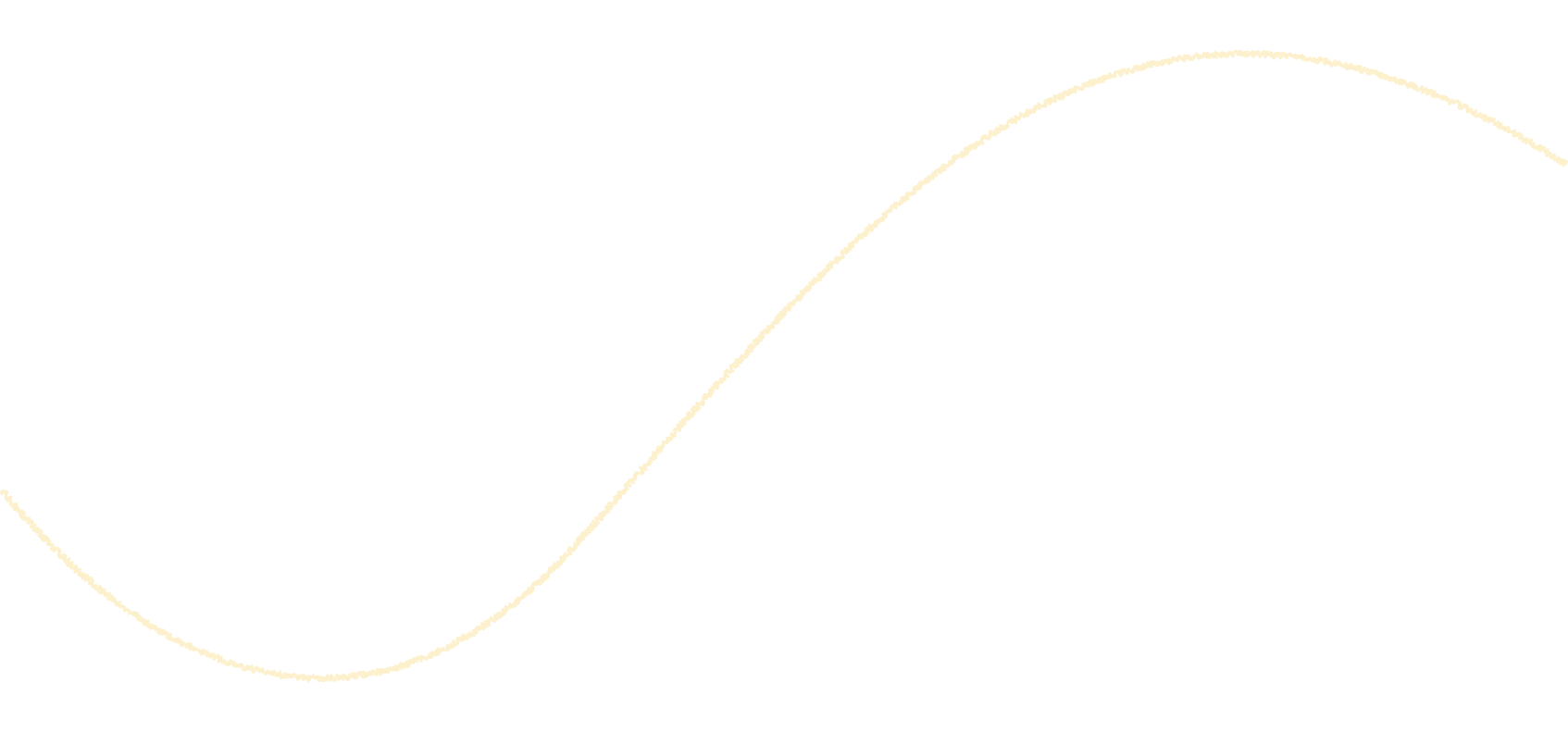
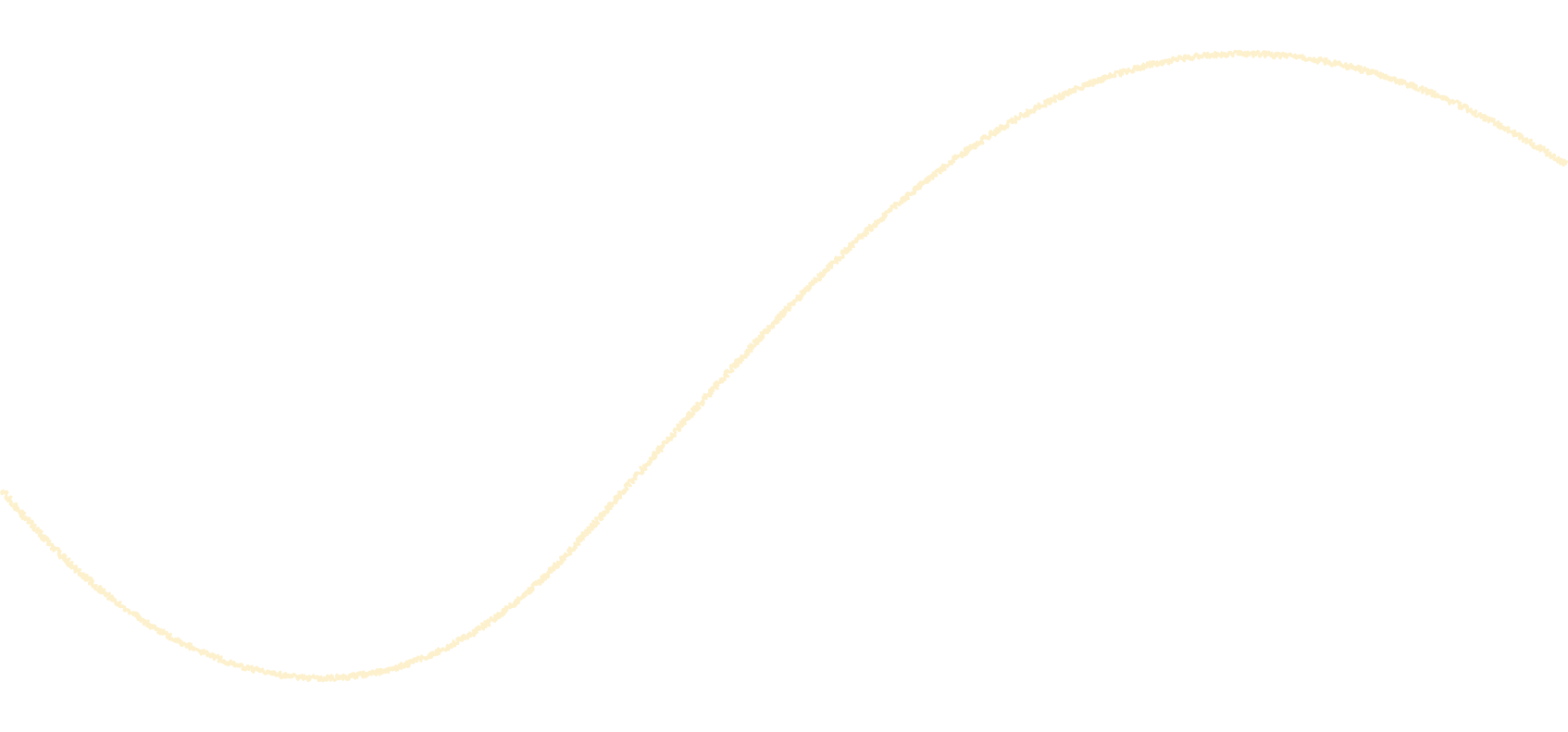
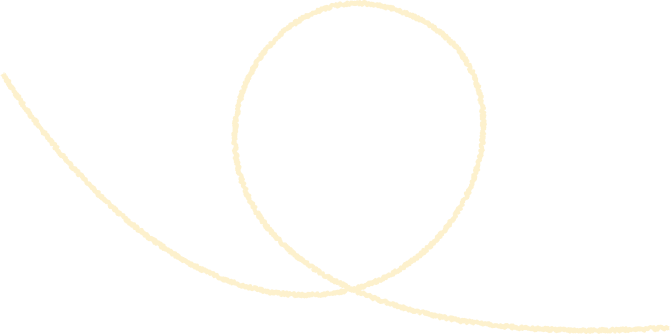
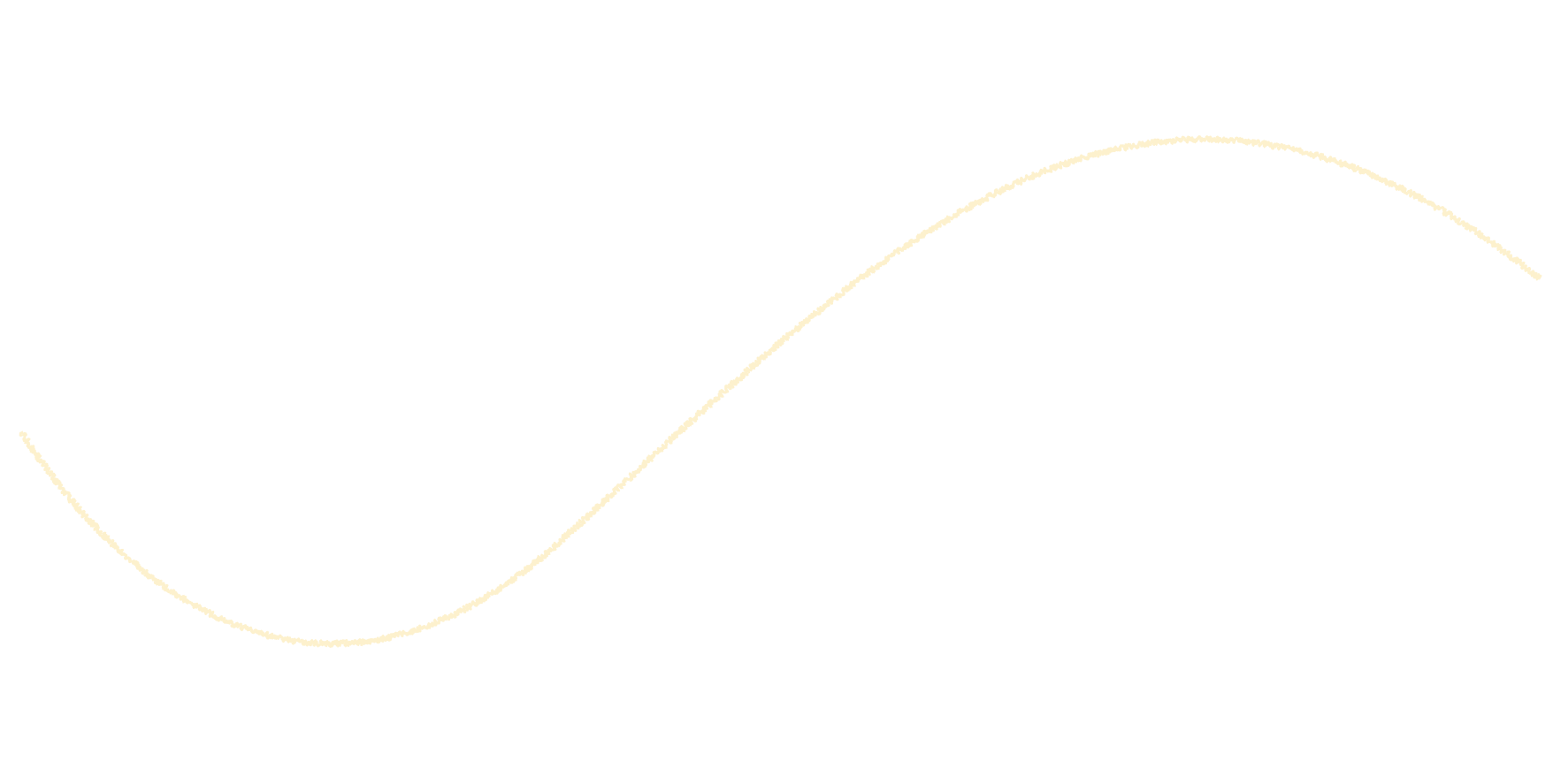
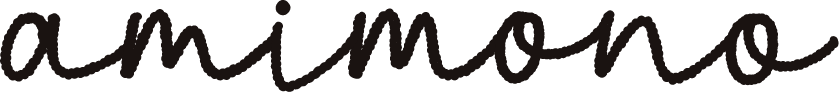



 ポスト
ポスト